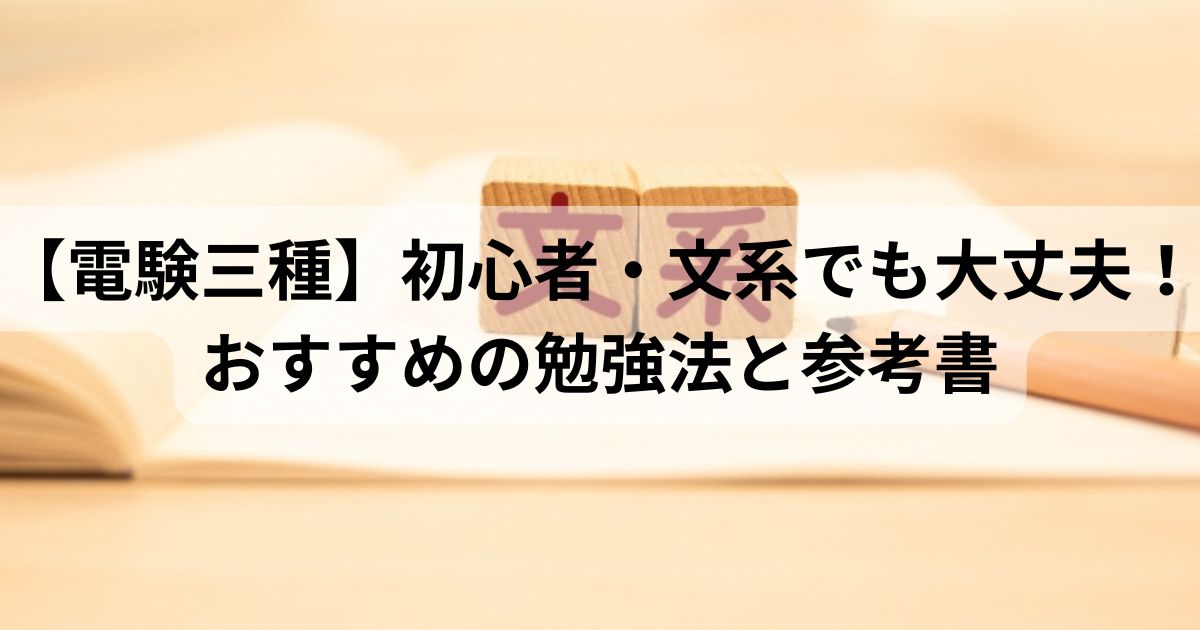電験三種って理系や電気の知識がないと無理?
数学に自信がなくて不安…。
そもそも何から始めたらいいの?
そんな不安を抱えている方へ。
私は勉強が得意ではない普通の社会人でしたが、独学&一発合格を達成できました。
文系・初心者でも合格できる道筋は、ちゃんと存在します。
この記事では、電験三種を初めて学ぶ方に向けて、
- 「なぜ難しいのか?」というリアルな体験談
- 最初に押さえておきたい電気や数学の基礎
- 文系や初心者でも理解できるおすすめ参考書
- 独学の進め方や、不安な方向けの勉強法
などを、できるだけわかりやすくお伝えします。
電験三種はたしかに簡単な試験ではありませんが、順番さえ間違えなければ誰でも合格を狙える試験です。
この記事があなたの一歩目のガイドになれば嬉しいです。
目次
電験三種の難しさとは?|初心者がつまずきやすい4つの壁
「電験三種ってそんなに難しいの?」
そう思っていた私も、勉強を始めてからその難しさに直面しました。
実際に合格して振り返ってみると、特に初心者や文系出身の方がつまずきやすいポイントは以下の4つだと思います。
- 学習範囲がとにかく広い!
- ただの暗記では解けない!“理解力”が試される
- 計算問題が多く、“数学が苦手”だと厳しい
- 電気って何?から始まる“イメージの難しさ”
それぞれ解説していきますね!
① 学習範囲がとにかく広い!
電験三種は【理論・電力・機械・法規】の4科目。
どれも専門的な内容で、しかも1科目ごとのボリュームもかなりあります。
たとえば「機械」だけでもこんなに内容があります👇
- 変圧器、直流機、誘導機、同期機
- 電動機応用
- 電気加熱、電気化学、照明
- パワーエレクトロニクス、情報、自動制御…など
参考書1冊で400ページ超えるのも当たり前。
それが4科目あるわけなので、初学者は「これ全部やるの…?」となると思います。
私も初めはスケジュールを立ててもなかなか終わらず、思っていたより長期間の勉強になりました。
② ただの暗記では解けない!“理解力”が試される
電験三種は、ただ公式を暗記して当てはめれば解けるような問題は少ないです。
- 公式を組み合わせて使う
- 問題文から必要な式を導く
- 単位や概念の理解が求められる
こういった“本質を理解しているか”を試すような問題が多いです。
私も過去問を初めて解いたとき、「教科書には載ってないタイプの問題ばっかり…」と感じました。
しかし、本質を理解することで初見問題も解けるようになりました。
近年は過去問ベースの出題が多くなっていますが、単純なコピー問題ではなく、応用力が必要なケースがほとんどです。
③ 計算問題が多く、“数学が苦手”だと厳しい
電験三種は実は“数学力”も重要。
特に理論科目では約8割が計算問題。機械や電力でも半分が計算問題です。
🔢 電験三種でよく使う数学要素
- 指数・対数
- 三角関数(sin, cos, tan)
- ベクトルの合成・分解
- 複素数(j記号、フェーザ表示)
- 一次・二次方程式
- 単位変換や比の計算
- 因数分解、展開
大学レベルの微分積分までは出ませんが、これらの計算が苦手だとかなり大変です。
私は最初は三角関数、指数・対数の計算とか忘れていましたが、理系出身なのですぐに思い出せました。
計算は練習すれば必ず慣れてきます。
でも、最初は「数学の壁」で挫折しそうになる人も多いと思います。
④ 電気って何?から始まる“イメージの難しさ”
電験三種の勉強を進めていく中で電気の基礎は必要不可欠です。
理論科目で基礎から学べるとはいえ、いきなり、
- インピーダンス
- 電圧、電位、電位差、電流
- 皮相電力、有効電力、無効電力、力率
などの電気用語が出てきても、イメージがつかめなくて???となる可能性があります。
しかも他の3科目(電力・機械・法規)も“電気の基礎知識がある前提”で話が進むので、まずは電気の世界に慣れることがとても大切です。
勉強が苦手だった私が独学で電験三種に一発合格できた理由とは?|理系出身+仕事の経験がカギだった
私は元々勉強が得意なタイプではなく、高校・大学ともに偏差値は40台。
しかも、大学を卒業してから10年以上勉強から離れていたので、勉強のやり方や習慣が身についていない状態でした。
そんな私でも、一発で合格できたのは以下の理由が大きかったと思っています。
- 理系出身で「最低限の数学力」があった
- 仕事で電気に触れていたから、イメージが湧きやすかった
逆に言えばこれらが理解できていれば電験三種は初心者でも合格できると考えています。
理系出身で「最低限の数学力」があった
私は一応理系の学部を出ていたので、数学に対する苦手意識はありませんでした。
とはいえ、
- 分数計算
- 因数分解・展開
- 一次・二次方程式
など、基礎的なところは何とか覚えていたというレベルで、
- 指数・対数
- 三角関数(sin, cos, tan)
- ベクトル
- 複素数(j記号やフェーザ表現)
- 解の公式
このあたりは完全に忘れていて、復習が必要でした。
ただ、「昔に習ったこと」なので、思い出すのにそれほど時間はかかりませんでした。
“ゼロから新しく覚える”のではなく、“思い出すだけ”だったというのが大きかったと思います。
仕事で電気に触れていたから、イメージが湧きやすかった
私の本業はメーカーで電気回路の設計をしています。なので、電験三種の勉強を始めた時点で、
- 電圧、電位、電位差、電流
- 直流と交流の違い
- 実効値・平均値・ピーク値
- 抵抗・コンデンサ・コイルの動き
- 直列・並列回路の基本
といった基礎的な知識やイメージはありました。
また、モータやパワエレも業務で扱っていたので、
「四機(誘導機・同期機など)」や「パワーエレクトロニクス」についても、ある程度イメージや知識がありました。
そのおかげで、理論科目や機械科目は比較的スムーズに理解できました。
むしろ、電力や法規の方が知らない内容が多くて大変でしたが、基礎がしっかりしていた分、対応できた感じです。
初学者でも「理論」と「機械」が分かれば戦える
これはあくまで私の体感ですが、
電験三種は理論と機械の2科目をしっかり理解できれば、残りの2科目(電力・法規)はなんとかなると思います。
理論=電気の基礎、機械=モータの基礎。
この2つを理解していると、電力や法規で出てくる内容も「あ、これは理論でやったな」とつながってくるんです。
文系・初心者でも電験三種に合格できる!まず身につけるべき“2つの土台”とは?
「電気のこと全然知らないし、数学も苦手なんだけど…」
そんな不安を持っている人に、まず最初に伝えたいのは――
“土台ができれば、電験三種はちゃんと戦える資格” だということです。
私自身、電験の勉強を始めたときは10年以上ぶりの勉強で、基礎を思い出すところからのスタートでした。
でも最初に以下の2つを押さえたことで、独学でも合格への道筋が見えました。
- 電験三種で必要な計算スキルを先に身につける
- 電気とモータの“イメージ”を先につかむ
電験三種で必要な計算スキルを先に身につける
正直、電験三種は“電気の資格”というより“数学の資格か!?”と思うくらい、計算問題が多いです。
理論はもちろん、機械・電力・法規でも普通に計算問題が出ます。
だからまず最初に、以下のような基礎的な数学のスキルは押さえておくのがおすすめです。
🔢 電験三種でよく出てくる数学の内容
- 指数・対数(10の何乗、log計算など)
- 三角関数(sin, cos, tan の使い方)
- ベクトル(合成・分解のイメージ)
- 複素数(j記号やフェーザ表現など)
- 単位の換算、比の計算
- 分数計算・平方根
- 一次・二次方程式、因数分解・展開
私も最初は忘れていたので、公式を見て「うわ…こんなのやったなぁ」と思い出しながら復習しました(笑)
でも、一度やったことがある内容なら思い出すのは意外と早いですし、実際に問題を解いていくうちに自然とスピードも上がっていきました。
文系の方は、まずはこのあたりの計算に少しずつ慣れるところから始めると良いと思います。
電気とモータの“イメージ”を先につかむ
数学の基礎がある程度できたら、次は電気の世界に慣れることです。
電験三種で最初に学ぶ「理論」科目は、電気の基礎がぎっしり詰まっています。
ここでつまずく人が多いのは、そもそも電気のイメージが湧かないからなんですよね。
私は回路設計の仕事をしていたので、電圧や電流の関係、抵抗、コイル、コンデンサの動作などは理解していました。
そのおかげで、理論科目の内容もスッと頭に入ってきました。
⚡ 電気の基礎として押さえたいポイント
- 直流と交流の違い(波形や意味)
- 電圧・電流・電位・電位差の関係
- 実効値・平均値・ピーク値の違い
- 抵抗・コイル・コンデンサの動き(エネルギーの蓄え方など)
- 並列回路と直列回路の違い
- 負荷とは?
これらは初心者向けの参考書でも、図解を使ってわかりやすく説明してくれているものがあります。
まずはそういった参考書やYouTubeの解説動画で、イメージを掴むことを重視してみてください。
さらに余裕があれば、モータの基本も知っておくと「機械」科目がグッと楽になります。
私は仕事でモータに触れていたこともあり、四機(誘導機・同期機など)やパワエレにも抵抗はありませんでした。
先に軽くでも以下のようなポイントをおさえておくと、理解が進みやすいです。
⚙️ モータについて押さえておくと良いポイント
- モータって何に使われているの?(身近な例から)
- 電気エネルギーと機械エネルギーの違い
- モータが回る仕組み(磁界と力の関係)
- モータの構造(ロータとステータの関係)
- 負荷電流・トルク・誘起電圧とは?
- 発電機と電動機の違い
電気初学者・文系におすすめの参考書
電験三種の勉強を始めたばかりの頃、電気やモータの基礎知識・イメージがあったからこそ理論や機械科目はスムーズに理解できました。
そんな経験から、電気や数学の“基礎”を固めることが、最短で合格につながると今では強く感じています。
ここでは、私自身が実際に使用したり、書店で手に取って「これは初心者にぴったりだ」と思った参考書をご紹介します。
【超入門】電験三種に必要な数学・電気の基礎が学べるおすすめ本
まずは電気や数学の超基礎から学びたい人向けにおすすめの2冊です。
私自身は使っていませんが、書店でじっくり立ち読みして「これは分かりやすい!」と感じた本です。
📘 みんなが欲しかった! 電験三種 合格へのはじめの一歩
📘 ゼロからスタート! 桜庭裕介の電験三種1冊目の教科書
どちらも共通しているのは、次のような点です👇
✅ この2冊のおすすめポイント
- 数学は「比の計算」や「一次方程式」など本当に基礎から解説
→ さらに指数・対数・複素数など、電験三種で必要な範囲まで無理なくカバー。 - 電気の説明がイメージで分かりやすい
→ 電位差=水位差、電圧=ピストンの力、電流=流れる水の量など、感覚的に理解できるよう工夫されている。 - 図やイラストが豊富で、読むのが苦にならない
- 電験三種の全体像や各科目の基礎やポイントを解説
難しい数式よりも、まずは「なるほど!そういうことか」と思えることが大事だと思います。
特に文系の方には、この“イメージの持ちやすさ”が非常に大きな武器になります。
モータが苦手な人こそ読んでほしい!図解で学べるモータの参考書
電験三種の「機械」科目では、モータの知識が避けて通れません。
私は新人の頃にモータの勉強をするのに下記の本は重宝しました。
どちらもモータの基礎だけでなく、モータを動かす為の電気の基礎も解説しています。
📗 図解入門よくわかる最新モータ技術の基本とメカニズム
→ 私が新人時代に買って今でも持っている一冊。図解中心で読みやすいです。
📕 史上最強カラー図解最新モータ技術のすべてがわかる本
→ こちらは私が上記の本を買った後に出た本ですが、職場の後輩たちに人気で、見せてもらったら確かにわかりやすかったです。
フルカラーで図も多く、内容も実用的。今から買うなら断然こちらがおすすめかもです。こちらの本はSNSなどを見る限り電験三種の勉強に使っている人も多く評判もいいです。
✅ モータ参考書の使い方アドバイス
- 電験三種専用の本ではないので、細かく暗記する必要はなし
- 「モータってこんなふうに動くんだな〜」とイメージを持つための読み物として使うのが◎
- 機械科目を本格的に勉強する前のウォーミングアップとして最適
- 機械科目を勉強している時に分からない時に辞書的に使うのも◎
SNSでもこの本を活用している受験生をよく見かけますし、「ああ、やっぱりイメージの力って大きいんだな」と改めて感じます。
参考書の選び方まとめ
どの参考書を選ぶか迷ったときは、「図やたとえ話が多くて、イメージがしやすいもの」を選ぶのがおすすめです。
理解できれば自然と覚えられるようになりますし、勉強のストレスも減ります。
自分に合った“入り口の1冊”が見つかれば、学習のスタートがグッと楽になりますよ!
一発合格を目指す!電験三種の具体的な勉強方法
数学や電気の基礎がある程度身についたら、あとは王道の参考書と過去問を使って、実践的な学習に進むだけです。
電験三種の試験範囲は広いですが、「何からどう勉強すればいいのか」がわかっていれば、初心者でも一発合格は十分狙えます。
私自身、効率よく進めるために意識していたポイントや、実際に効果があった勉強法をまとめた記事がありますので、これから本格的に学習を始めたい方はぜひ参考にしてみてください👇
まとめ|文系・初心者でも電験三種は合格できる!
電験三種はたしかに難関資格ですが、正しいステップを踏めば、文系出身や電気初心者でも一発合格は十分可能です。
この記事でお伝えした通り、
- まずは「数学の基礎」と「電気・モータのイメージ」をしっかり押さえる
- 難しい参考書にいきなり飛びつかず、やさしい導入書から入る
- 適切なタイミングで過去問や実践的な問題演習に移行する
といった手順で進めれば、合格に近づけます。
私自身、文系ではありませんが勉強が得意だったわけではありません。
それでも、一つずつ「理解してから進む」を心がけたことで、合格までたどり着けました。
電験三種の勉強は長期戦になりがちですが、正しいやり方で地道に続ければ必ず成果は出ます。
焦らず、自分のペースで進めていきましょう!
今後も「電験三種の勉強法」や「おすすめ参考書」など、役立つ情報を更新していきますので、ぜひ他の記事もチェックしてみてくださいね。
独学が不安な方へ
「独学だけで本当に合格できるかな…?」
そんな不安がある方は、通信講座をうまく活用するのも一つの手です。
最近は、電験三種の初学者向けに「数学・電気の基礎」から丁寧に学べる講座も増えています。
✅ 通信講座のメリット
- 試験に出やすい分野に絞ったカリキュラムで、最短ルートで合格を目指せる
- プロ講師によるわかりやすい講義で、苦手分野もスッと理解できる
- 質問対応・添削サポート付きなので、疑問を残さず前に進める
- 参考書選びで迷わないのも意外と大きな時短ポイント
効率よく合格を目指したい方、勉強の習慣化が不安な方はチェックしてみてください。