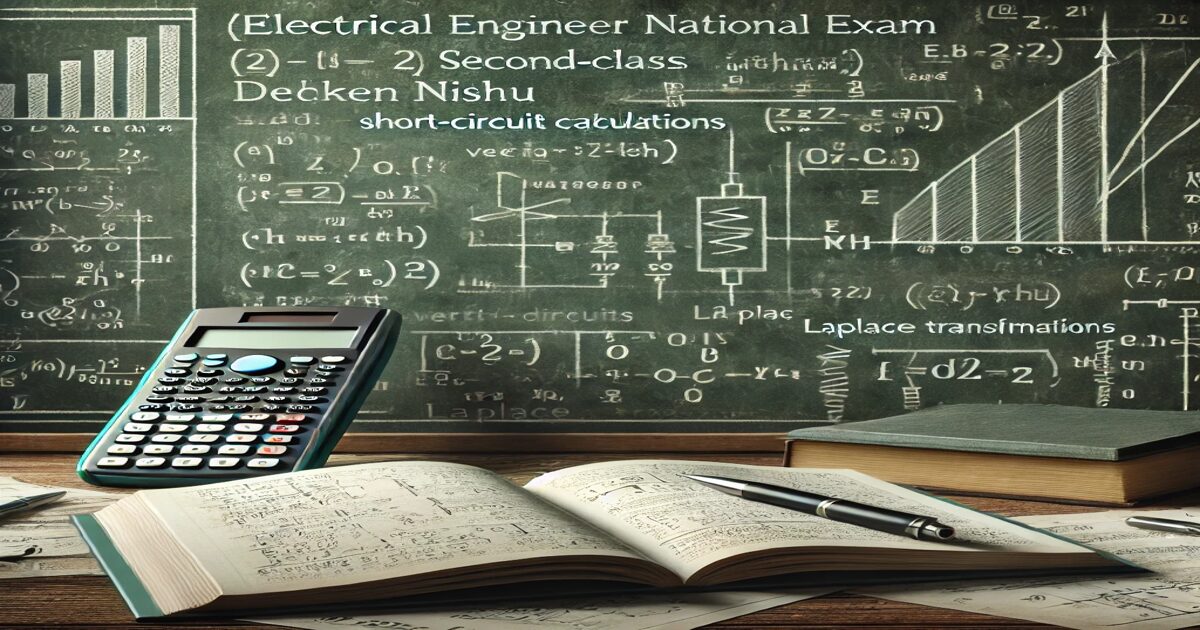電験二種二次試験の計算問題は電験三種と比べると難易度が非常に高いのが特徴ですが、
「分野ごとの出題傾向は?」
「対策のポイントは?」
「どの分野が特に難しいの?」
と気になる方も多いのではないでしょうか。
私自身、高学歴でもなく、勉強が得意だったわけではありません。それでも独学で電験二種に合格することができました。
この記事では、私が実際に使用した複数の問題集と、令和6年度の試験を受験したリアルな体験をもとに、「計算問題の分野別の傾向と難易度」「対策のポイント」をわかりやすく解説します。
どの分野に重点を置くべきか、どうやって得点源を作るか、
これから電験二種の合格を目指す方にとって参考になればうれしいです!
目次
🔍 過去問から見る計算問題の傾向と難易度
電験二種二次試験の計算問題は、分野ごとに難易度や出題傾向が異なります。
私は実際に「完全攻略」で平成7年度~平成30年度の問題を解き、さらに本番対策として令和1年~5年の過去問や、「戦術」で旧制度の問題にも取り組みました。
この経験から、分野別の難易度や特徴、傾向をお伝えします!
以下の特徴や難易度は、私が電験二種二次試験の勉強を通して感じたものを独断と偏見で語ったものです(笑)。
ですが、少しでも参考になれば幸いです! 😊
⚡️ 電力管理の計算問題の特徴と難易度
電力管理は各分野から満遍なく出題される傾向があり、以下のような特徴があります。
- 送電の短絡計算や施設管理の負荷率を求める問題、水力発電の計算は、電験三種の計算問題を難しくしたイメージで取り組みやすいです。
- しかし、分布負荷や一線地絡電流の計算などは三種では出題されない分野であり、難易度・計算量ともに高いです。
本番では、計算量や難易度の差を見極めて、解きやすい問題を選択する判断力が重要になります。
💧 水力発電
- 特徴:三種の問題を少し難しくしたイメージで、簡単な公式で解ける問題が多い
- 計算量:少ない
- 難易度:低め
- 対策ポイント:
解法も簡単で計算量が少ないため、計算ミスのリスクも低く短時間で解答できるのが特徴です。
ただし、積分を含む問題が出題されることもあり、計算量が多くなるため、計算ミスが発生しやすいです。
🔥 火力発電・原子力発電
- 特徴:新制度では計算問題の出題がない
- 計算量:―
- 難易度:―
- 対策ポイント:
新制度以降、計算問題は出題されていません。論説対策を重視しましょう。
⚡️ 送電・変電・配電
- 特徴:三種とは全く異なる毛色の問題が多く、問題自体の難易度が高い
- 計算量:多い
- 難易度:高い
- 対策ポイント:
送電・変電・配電は複雑な解法や計算が多く、時間がかかる問題が多いですが、出題頻度が多い分野です。
計算量が多いので、計算ミスが発生しやすく注意が必要です。
🛠️ 施設管理
- 特徴:三種の難易度を高くしたイメージだが、概算や単純な計算が多い
- 計算量:少なめ~普通
- 難易度:やや低め~中
- 対策ポイント:
計算自体は単純な問題が多いですが、問題によっては解答に時間がかかるケースもあります。
短時間で解ける問題を見極めるのがカギ!
⚙️ 機械制御の計算問題の特徴と難易度
機械制御は電力管理とは異なり、三種の問題を難しくしたような内容で、出題傾向がはっきりしているのが特徴です。
比較的解きやすい問題も多いものの(年度によっては非常に難しい問題が出ることもあります)、計算問題が中心のため、時間が足りなくなりやすい傾向があります。
そのため、考えている時間はほとんどなく、問題を見た瞬間に解法がパッと浮かぶレベルまで演習を重ねることが重要です。
最終的には、機械的に解けるレベルまで仕上げるのが理想ですね。(機械制御だけに…😏)
- 問1・問2:四機(変圧器・直流機・誘導機・同期機)から2問
- 問3:パワーエレクトロニクス
- 問4:自動制御
➡️ このように出題分野が固定化されているため、対策が立てやすいです。
🔌 変圧器
- 特徴:三種と比べると計算量が多いが、解法は比較的シンプル
- 計算量:普通~やや多め
- 難易度:中
- 対策ポイント:
電験三種と比べると計算量が増えますが、パターンを押さえていれば解ける問題が多く、四機の中でも出題頻度が多い分野です。
計算量が多い分、計算ミスに注意!
🔋 直流機
- 特徴:三種の問題を少し難しくしたイメージで、簡単な公式で解ける
- 計算量:少ない
- 難易度:低め
- 対策ポイント:
直流機は計算量が少なく、短時間で解ける問題が多いですが、二種ではチョッパ回路を含む問題が出題されることがあり、難易度が高く時間がかかる場合があります。回路図を書けるようにするのがポイント。
ただし、出題頻度は低く、平成25年以降は出題されていません。
🔄 誘導機
- 特徴:三種と比べると計算量は多いが、解きやすい問題が多い
- 計算量:やや多め
- 難易度:やや低め~中
- 対策ポイント:
同期機や変圧器と比べると、比較的解きやすい問題が多いのが特徴です。対策のポイントは、等価回路を理解し、描けるようにすることと、導出後の公式を暗記しておくこと。
ただし、トルクの比例推移に関する問題は難易度が高めなので、比例推移の仕組みや計算方法をしっかり理解しておくことが重要です。
なお、近年は出題頻度が減少傾向にあります。
⚙️ 同期機
- 特徴:複雑な解法を用いたベクトル計算が多い
- 計算量:多い
- 難易度:高め
- 対策ポイント:
四機の中で最も難易度が高い分野です。
複素数計算やベクトル図を用いた問題が多く、計算量が多く時間がかかるため、本番では注意が必要です。ベクトル図を理解して書けるようにするのがポイントです。
💡 パワーエレクトロニクス
- 特徴:複雑な波形や積分計算がある
- 計算量:多い
- 難易度:非常に高い
- 対策ポイント:
私自身は未対策のため、詳細な難易度は判断できませんが、非常に難しい分野とされています。
複雑な波形や積分計算が絡むため、計算量も多く、解法パターンも多いとされています。そのため、パワーエレクトロニクスを専門にしていない場合は、本番で見送る選択肢も視野に入れてOKです。
ちなみに、私自身は仕事で多少パワーエレクトロニクスを扱っていましたが、この分野は思い切って捨てました。
📊 自動制御
- 特徴:解法パターンが決まっているが文字計算が多い
- 計算量:やや多め
- 難易度:やや高め
- 対策ポイント:
典型的な問題パターンを押さえれば攻略しやすい分野です。さらに、毎年必ず出題されるため、優先的に対策するのが望ましいでしょう。
また、二種では三種にはないラプラス変換が出題されるため、最初は戸惑うかもしれませんが、繰り返し演習を重ねることで機械的に解けるようになります。
ただし、文字計算が多いため解答に時間がかかりやすく、計算ミスにも注意が必要です!
🔥 近年の傾向と対策の狙い目
💡 近年の傾向
- 機械制御では同期機の出題が増加傾向!
➡️ インバータの普及による影響か、近年は同期機の出題が多くなり、誘導機は減少傾向です。 - 直流機は出題頻度が低い!
➡️ 平成25年以降は出題がありません。
⚡ 電力管理の狙い目は計算が比較的シンプルな「水力発電」「施設管理」!
ただし、本番では論説問題と計算問題のどちらが出題されるかは分かりません。
また、二次試験では全分野がまんべんなく出題される傾向があるため、特定の分野だけに偏らず、バランスよく学習することが重要です。
⚙️ 機械制御の狙い目は「自動制御」「変圧器」「誘導機」!
- 自動制御は毎年出題されており、典型的な問題が多いため、パターンを押さえれば攻略しやすい分野です。ただし、年度によっては難問が出ることもあるので注意が必要です。
- 変圧器は出題頻度が高く、しっかり対策しておくべき分野です。
- 誘導機は出題頻度は減少傾向にありますが、比較的解きやすい問題が多いため狙い目です。
- 直流機は問題自体はシンプルで解きやすいですが、出題頻度が低いため、優先度は下げてもOKです。
✅ まとめ:過去問で傾向を掴むのが合格への近道!
実際に過去問を解いてみると、分野ごとに計算量や難易度が大きく異なることが分かります。
以下に電力管理・機械制御の分野毎の計算量と難易度をまとめておきます。
⚡️ 電力管理
| 分野 | 計算量 | 難易度 |
|---|---|---|
| 水力発電 | 少ない | 低め |
| 火力・原子力発電 | ー | ー |
| 変電・送電・配電 | 多い | 高い |
| 施設管理 | 少なめ~普通 | やや低め~中 |
⚙️ 機械制御
| 分野 | 計算量 | 難易度 |
|---|---|---|
| 変圧器 | 普通~やや多め | 中 |
| 直流機 | 少ない | 低め |
| 誘導機 | やや多め | やや低め~中 |
| 同期機 | 多い | 高め |
| パワーエレクトロニクス | 多い | 非常に高い |
| 自動制御 | やや多め | やや高め |
✅ 本記事のまとめポイント
- 本番では、計算量が少なく短時間で解ける問題を優先する
- 複素数計算や積分を含む問題は時間がかかるため注意!
- 出題傾向は安定しているので、過去問演習でパターンを把握するのが合格への近道です!
📚 この記事では、私が実際に過去問を解いた経験をもとに分野別の特徴や難易度を解説しました。
本番での問題選択や時間配分に役立てていただけたら嬉しいです! 💪✨