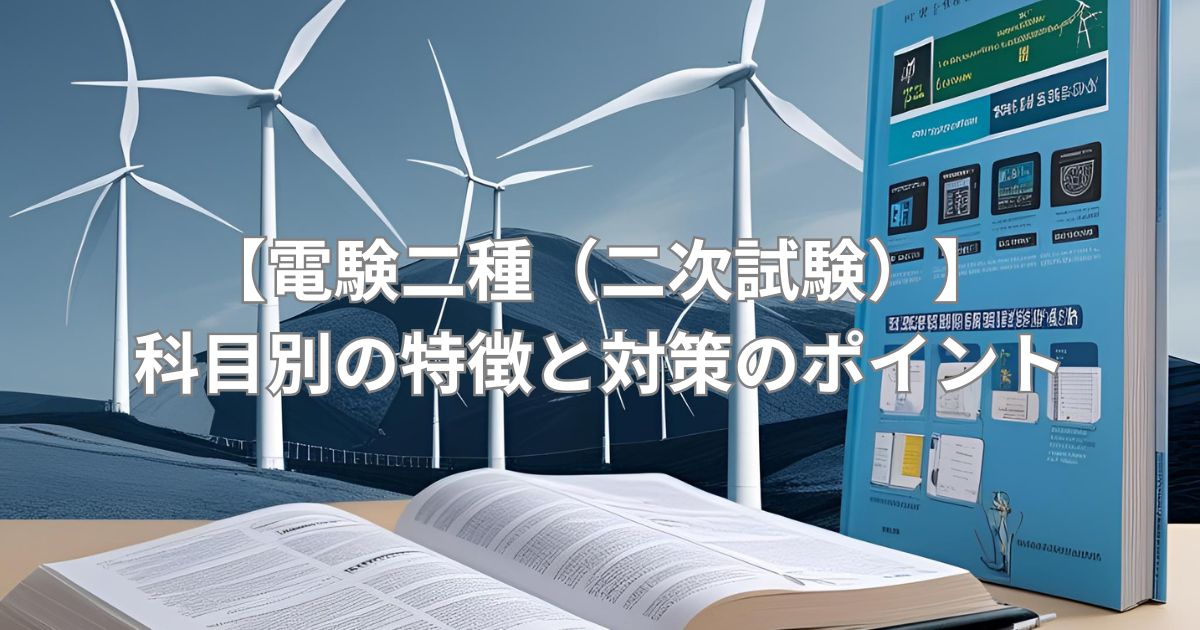電験二種の一次試験を突破してホッとしたのも束の間、待ち構えているのが“本番”ともいえる二次試験です。
記述式の出題に加え、計算も論説も問われるこの試験は、単なる知識だけでは太刀打ちできない難関。
さらに、出題形式や時間配分、科目ごとの戦略を誤ると、どれだけ勉強しても結果につながらないことも珍しくありません。
私自身、二次試験には相当な苦労をしました。
でも、その経験があるからこそ、どんな対策が有効だったか、どんな勉強法が遠回りだったかを、リアルにお伝えできます。
この記事では、電力管理・機械制御それぞれの特徴や攻略のポイントを、実体験をもとに詳しく解説しています。
はじめての二次試験で何から手を付けるべきか悩んでいる方や、今の勉強法に不安がある方にとって、きっと役立つはずです。
目次
🔍 電験二種二次試験の概要|まずは試験の全体像を押さえよう
一次試験を突破した人だけが挑戦できる「電験二種の二次試験」は、いわば最終関門。
計算と論説の記述式で構成され、合格率はわずか10〜20%と非常に厳しい試験です。
まずは、試験の構成や科目の特徴をしっかり理解しておきましょう。
✅ 試験の基本情報まとめ
- 試験科目:電力管理、機械制御の2科目
- 出題形式:記述式(計算+論説)
- 出題数と選択方式
- 電力管理:6問中4問を選んで解答
- 機械制御:4問中2問を選んで解答
- 試験時間
- 電力管理:120分
- 機械制御:60分
- 配点と合格基準
- 電力管理:120点満点(30点×4問)
- 機械制御:60点満点(30点×2問)
- 合格基準:2科目合計で60%(180点中108点以上)かつ各科目で平均点以上
※年度によっては合格基準の引き下げあり
このように、単に全体で6割を取ればいいというわけではなく、両科目でバランスよく得点することが求められます。
一方の科目で高得点でも、もう一方が平均以下だと不合格になるため、苦手科目の放置はNGです。
次のパートでは、各科目の特徴や対策のポイントを詳しく解説していきます。
📌 科目別の特徴と対策のポイント
ここでは私が実際に電験二種二次試験の学習を通じて得た知識や経験をもとに各科目毎の特徴や難易度、対策のポイント、私が実践した学習戦略まで解説します。
- 電力管理の特徴と対策のポイント
- 機械制御の特徴と対策のポイント
⚡ 電力管理|バランス重視の姿勢がカギ!
電力管理は、計算問題と論説問題がバランスよく出題されるのが大きな特徴です。
ここ数年は、6問中3〜4問が論説問題という年もあり、論説の比重が少し高めになっています。
試験時間は120分とたっぷりありますが、計算1問に30分以上かかることもあるため、決して油断はできません。
🔢 計算問題の特徴と難易度
私が実際に電力管理の計算問題を解いてみて感じた特徴や難易度はこんな感じです👇
- 変電・送電・配電分野の問題は、三種とは全く異なる難しさで、計算量も多く非常にハード。
- 単位法や複素数、解の公式などを駆使する問題も多く、計算結果が細かい・桁が大きくなるため計算ミスのリスクも高い。
- 1問に平均30分前後かかる印象で、見直し時間も必要。
- 過去問と似たようなパターンが多いため、解法パタンマスターで得点源にできる一方、計算ミスや解法の誤適用で大きく失点する可能性も。
🧠 論説問題の特徴と難易度
一方、論説対策を通じて感じた特徴や難易度はこんな感じ👇
- 範囲が広く、記述で再現できるレベルまでの暗記が必要。その分、対策には時間がかかる。
- 過去問の類題は少なく、完答はかなり難しいが、計算問題のように大きく失点するリスクが少ないので部分点は狙いやすい。
- 1問あたり15分程度で解答可能なため、時間配分に余裕が生まれる。
📌 対策のポイント|「計算特化」の時代は終わりつつある?
私自身もそうでしたが、よく「電力管理は計算問題に特化して対策すればOK」と言われます。
しかし最近の傾向を見る限り、それはやや危険な戦略だと感じました。
- 論説問題の比率が高くなっている。
- 計算は難問・奇問が混ざることもあり、どれだけ対策しても完答できない問題がある。
- 逆に論説は覚えておけば確実に点が取れるので、リスク分散の意味でも両方バランスよく学習すべきです。
私の場合、実際の試験や過去問での本番シミュレーションで、計算と論説あわせて6問中「これはいけそう」と思えたのはどれも4問程度。つまり、論説問題にも救われた形でした。
🎯 私が意識した学習戦略
私が電力管理の対策で意識した戦略は以下の通りです👇
- 論説は暗記中心の為、早くから初めても試験までに忘れてしまう可能性があります。私は前半は計算問題を中心に学習し、後半から論説の暗記に取り組みました。その間後半も計算問題の復習は継続していました。
- 計算は「なぜこの式、解法を使うのか」まで理解しないと、似たような問題でミスします。特に変電・送電・配電の分野は似たようで違う問題が出るので注意。私は過去問を何周もして、解法パターンを習得するだけでなく、各問題の細かな違いや意図まで気づけるレベルまで仕上げました。
- 論説は答えの丸暗記ではなく、知識量を増やすことと自分の言葉で説明できるようにするのが大事。出題の切り口が変わっても対応できるようになります。
- 選択した4問のうち、2問を確実に取り、残り2問は部分点狙いの戦略が現実的。高得点は狙いつつ、最低6割を確保できるバランス力がカギになります。
⚙️ 機械制御|瞬発力と正確性がモノを言う
機械制御は、ほぼ計算問題オンリーの科目です。
しかも、出題される分野はある程度パターン化されていて、対策が立てやすいのが魅力です。
ただし、試験時間はたったの60分。
計算2問解くには考えている暇がないため、反射的に解法が出てくるレベルの演習量が求められます。
🔍 出題傾向と難易度
- 問1・問2 → 四機(変圧器、直流機、誘導機、同期機)
- 問3 → パワーエレクトロニクス
- 問4 → 自動制御
出題範囲がはっきりしており、年度によって構成も大きくは変わりません。
そのため、効率的な対策が可能です。
🔢 計算問題の特徴と難易度
私が実際に機械制御の計算問題を解いてみて感じた特徴や難易度はこんな感じです👇
- 電力管理と比べて型にはまった問題が多く、満点も狙いやすい。
- とはいえ、年度によってはひと筋縄ではいかない難問も出るので、解ける問題の見極めと取捨選択も重要。
- 四機分野は頻出ですが、例えば直流機は10年以上出題がないなど、優先度を見極めた対策が必要です。
🧠 論説問題について
論説問題はほとんど出題されません。
実際に私も論説対策は一切やっていませんでした。
📌 対策のポイント|「機械的に解ける」状態を目指す
機械制御は解法パターンの習得も大事ですが、とにかくスピードと正確さを意識して学習しました。
正直、機械制御って考えている時間がなく、機械的に解かないと時間内に解けなくて、これ何ゲーだよ(笑)と思いました。
- 計算問題特化の勉強でOK。
- 苦手な分野は捨てるのもアリ。私はパワエレを捨てて、他の分野に集中しました。
- 電力管理と同様、解法の理解が重要。ただの暗記では、少し問われ方が変わっただけで詰まってしまいます。
- 加えて、スピードと正確さが最重要。制限時間60分では、1問30分でもギリギリ。1問25分以内に仕上げる意識が必要です。
🎯 私が意識した学習戦略
私が機械制御の対策で意識した戦略は以下の通りです👇
- とにかく1問にかかる時間を意識して「反射的に手が動く」状態まで演習を繰り返す。
- 公式解答を参考に減点されないレベルで最低限の記述に留める。
- 毎年難易度に波がありますが、目標は満点、最低でも8割を狙う気持ちで臨むことが大切です。
私が受験した令和6年度の機械制御は比較的易しく、満点に近い得点が取れたと思います。
📝 まとめ|二次試験は「バランス」と「演習量」が合格のカギ
電験二種の二次試験は、記述式という特性上、「知っている」だけでは太刀打ちできない難関です。
私自身、計算・論説どちらも想定外の問題が出て戸惑う場面がありましたが、「いける問題を確実に拾う」戦略で何とか合格を勝ち取ることができました。
二次試験で大切だと感じたポイントを最後に振り返っておきます。
⚡ 電力管理
計算問題、論説問題ともに難易度が高く、しっかりとした理解・対策が必要
⚙️ 機械制御
時間配分、計算ミスが合否を分ける!計算の正確さとスピードが命
✅ 合格へのポイントまとめ
- 電力管理は論説問題の比率が高まっているため、計算一辺倒では危険。
→ 論説対策にも一定の時間を割くことが重要。 - 計算問題は理解ベースの対策が不可欠。
→ 解法の丸暗記だけでなく「なぜその式・解法になるのか」を押さえておく。 - 論説問題は部分点狙いでもOK。
→ 満点は難しいが、知識の再現力がものを言う。 - 機械制御は計算に特化し、素早く正確に解く練習が必須。
→ 「時間との戦い」であり、手が勝手に動くレベルを目指す。 - 捨て問・捨て分野の判断も戦略のうち。
→ 全問対応は難しいからこそ、取れる問題に集中する。 - 電力管理で最低6割、機械制御で最低8割を狙う
本番で何が出るかは分かりません。
でも、どの問題が来ても「この中なら、この問題はいける!」と思えるように準備することが、合格への一番の近道です。
あなたの努力が実を結ぶよう、心から応援しています!