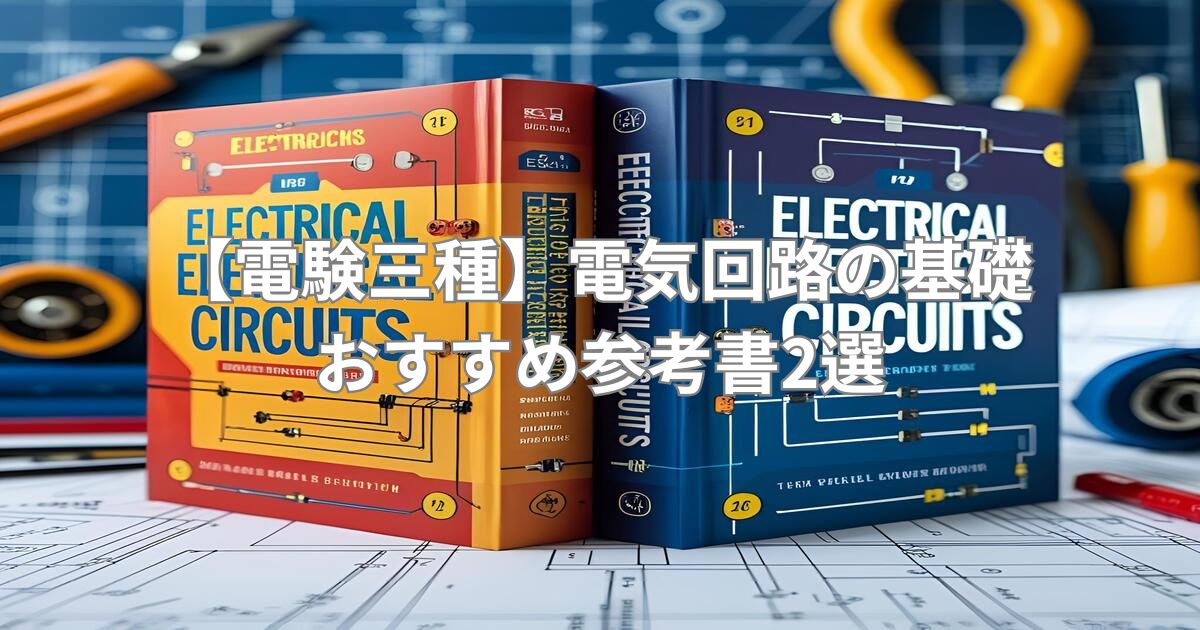「電気系の会社に入ったけど、全然理解できない…」
「電圧とか電流とか言われても、正直よく分からない…」
そんな風に感じていませんか?
実は、私自身もまったく同じ状況からのスタートでした。
大学は電気電子工学科でしたが、暗記中心の勉強で理解はあいまいなまま。
回路設計の仕事に就いた当初は、電圧・電流・電位・電位差の違いさえよく分からず、本当に苦労しました。
それでも、基礎から学び直しながら経験を積み、今では回路設計エンジニアとして働きつつ、電験三種にも独学で一発合格することができました。
この記事では、電験三種を目指す方はもちろん、
「これから電気の勉強を始めたい」
「仕事で電気に関わるけど、イメージがつかめない」
そんな電気初学者・文系出身者・新人エンジニアの方にも役立つ内容をお届けします。
- なぜ電気が難しく感じるのか(実体験ベース)
- 電気初心者が最初に押さえるべき基本ポイント
- 電験三種や実務に役立つ、図解で学べるおすすめ参考書
- 独学に不安がある方向けの勉強サポート方法
など、「これから電気を学ぶ方」向けに、わかりやすく丁寧に解説しています。
この記事が、あなたの「電気の世界へ踏み出す第一歩」になれば嬉しいです。
目次
🤯 電気初学者・文系が電験三種や電気回路でつまずく理由
私は理系出身で、大学では電気電子工学を学びました。
一応、電気回路の授業も受けていたはずなんですが──正直、あまり理解できていませんでした。
社会人になって回路設計の仕事に就いたとき、改めて「自分、電気のこと全然分かってないな…」と痛感。
そこから本格的に電気回路の勉強を始めたのですが、最初は本当に苦労しました。
特にこんな用語が出てくると、完全に頭がフリーズします。
- インピーダンス
- 電圧と電位の違い
- GNDとアースの違い
- 有効電力・無効電力・皮相電力
- 力率ってそもそも何?
当時はGND=アース=0Vだと思っていました(笑)
学生時代はなんとなく式を覚えてテストを乗り切っていたけれど、
「なぜそうなるのか?」
「実際の現場でどう関係するのか?」
「用語は知っているけど、ちゃんと理解できていない」
という状態でした。
🧱 実務で学んだ“基礎の重要性”
私が電気回路を本気で勉強し直したのは、新人時代に実務で必要に迫られてからです。
今回ご紹介する入門書もそのときに読みました。
図解中心でとにかくわかりやすく、電気の世界をイメージでつかむのに本当に助けられました。
この本で「電気の基礎」をつかんだうえで現場の経験を重ねていったことで、ようやく少しずつ理解が深まった感覚があります。
その後、電験三種の勉強を始めたときには、すでに電気の基礎やイメージがある程度身についていたので、最初の壁を感じずにスムーズに学習を進められました。
だからこそ、こう思います。
- 文系出身や電気初学者の方にとって、電験三種は最初の用語の時点でつまずく可能性が高い
- 「理論」でつまずくと、他の科目(電力・機械・法規)も理解しづらくなる
- 実務においても、経験だけでは限界があり、基礎知識があるかどうかで吸収力が変わる
💡 特にこんな人は要注意!つまずきポイント
- 文系・未経験で電験三種に挑戦している
- 「電圧と電位の違い」などの電気用語が曖昧なまま進めている
- 教科書を読んでもピンとこない
- 電気のイメージが頭に浮かばない
- 仕事で電気を扱うことになったが、用語の意味があやふや
電験三種の受験勉強でも、仕事で電気を扱ううえでも、最初に「電気ってこういうものか」とイメージできることが何より大切です。
そのために、図解が豊富でやさしく解説された入門書を1冊読むだけで、理解のスピードが劇的に変わります。
📌 電気初学者・文系が最初に押さえておきたいポイント
私は現在、電気機器メーカーで回路設計の仕事をしています。
大学は電気電子工学科を卒業していますが、正直、定期テストは暗記でなんとか乗り切っていたので、電気の基礎知識やイメージはほとんどないまま社会人になりました。
そんな状態で現場に出ると、いきなりつまずきます。
たとえば──
- 実効値とピーク値の違いがよくわかっていない
- 直流と交流の違いが曖昧
- 抵抗・コンデンサ・コイルの基本動作がイメージできない
- 回路図を見ても電気の流れや動作が分からない
こうした**“基礎中の基礎”が分かっていないと、設計や評価の場面で困ることばかり**でした。
私はそんなとき、図解中心の入門書を使って、あらためて電気の勉強をやり直しました。
電験二種まで取得した今では、その当時のパワハラ上司より電気の知識はある自信ありますけどね!!!(笑)
⚡ 最初に押さえておきたい電気の基礎
文系の方や初学者の方は、以下のようなポイントを図解付きの入門書などでまず押さえることをおすすめします。
- 直流と交流の違い(波形や意味の理解)
- 電圧・電流・電位・電位差の関係
- 実効値・平均値・ピーク値の違い
- 抵抗・コンデンサ・コイルの働き(エネルギーの蓄え方など)
- 直列回路と並列回路の違い
- 回路図を見て、電気の流れや動作がイメージできる
- 「負荷」とは何か?
これらは、テキストだけではイメージしにくいものも多いですが、図やカラーで視覚的に解説してくれる入門書なら、初心者でも理解しやすいです。
最近ではYouTubeなどでも丁寧な解説動画が出ているので、参考書+動画の組み合わせで「電気のイメージ」をしっかりつかむことが、最初の一歩として非常に効果的です。
🔑 電験三種の「理論」は“基礎の理解”がカギ
その後、電験三種の勉強を始めたときには、仕事を通じて電気の基礎やイメージがある程度身についていたおかげで、「理論」科目も比較的スムーズに理解できました。
実際、電験三種では「理論」以外の科目──電力・機械・法規も、“理論の知識があることを前提”に話が進んでいきます。
だからこそ、最初の段階で「電気の基礎をしっかり理解しておくこと」が、その後の学習全体を楽にしてくれるんです。
📖 参考書の選び方:まずはイメージから入るのが正解!
電気の勉強って、どうしても**「数式」「理論」「記号」**といった、固くてとっつきにくいものが先に出てきますよね。
でも、私の経験上、最初は細かい理屈よりも“イメージでざっくり理解すること”が大事だと思っています。
イメージがつかめると、数式もただの暗記じゃなく「意味を持ったツール」として自然に頭に入ってきます。
特にイメージと理論が繋がると超気持ちいいです!!!(笑)
きっと頭の中が共振するでしょう!(笑)
なので、参考書を選ぶときは以下のような点をチェックすると◎です👇
- 図やイラストが豊富で、視覚的にわかりやすい
- 身近なたとえ話(電位差=水位差、電流=水の流れなど)が使われている
- 難しい用語が出てきても、かみ砕いて説明されている
- 専門書っぽさよりも「読みやすさ・親しみやすさ」がある
「イメージできてから理論的なことを覚える」スタイルの方が、勉強のストレスも減りますし、モチベーションも保ちやすいですよ!
📚 電気初学者・文系におすすめ!電気の基礎が学べる参考書2冊
ここでは、私が新人時代に実際に使ってよかった本/本屋でじっくり読み込んで「これは分かりやすい!」と感じた本を2冊ご紹介します👇
この2冊は電験三種の勉強に使っている人も多く、電気初学者・文系でも分かりやすいと評判でした。
✅ 共通しているおすすめポイント
- 電気の基礎からていねいに解説
電気回路(オームの法則など)に入る前に「電圧って何?」「電流ってどう流れるの?」から始まる - イメージしやすいたとえが豊富
水の流れや高さに例えて、抽象的な電気の概念が感覚で理解できる - 図解&イラストが多く、読むのが苦にならない
- 電験三種の「理論」科目の内容もカバー
直流回路、交流回路、静電気、三相交流など基礎範囲を広くカバー
👤 こんな人におすすめ
- 電験三種の「理論」の参考書が難しくて何を言ってるか分からない…という方
- 数式の前にまず「電気の感覚」をつかみたい方
- 回路設計など電気系の仕事に就いたばかりの新人・初学者
📕 おすすめの使い方
- 電験三種の学習の前に導入として読む
- 勉強で詰まったときの補助教材として使う
- 実務や回路設計の入門として活用する
📗 図解で分かるはじめての電気回路|新人時代に実際に使った一冊
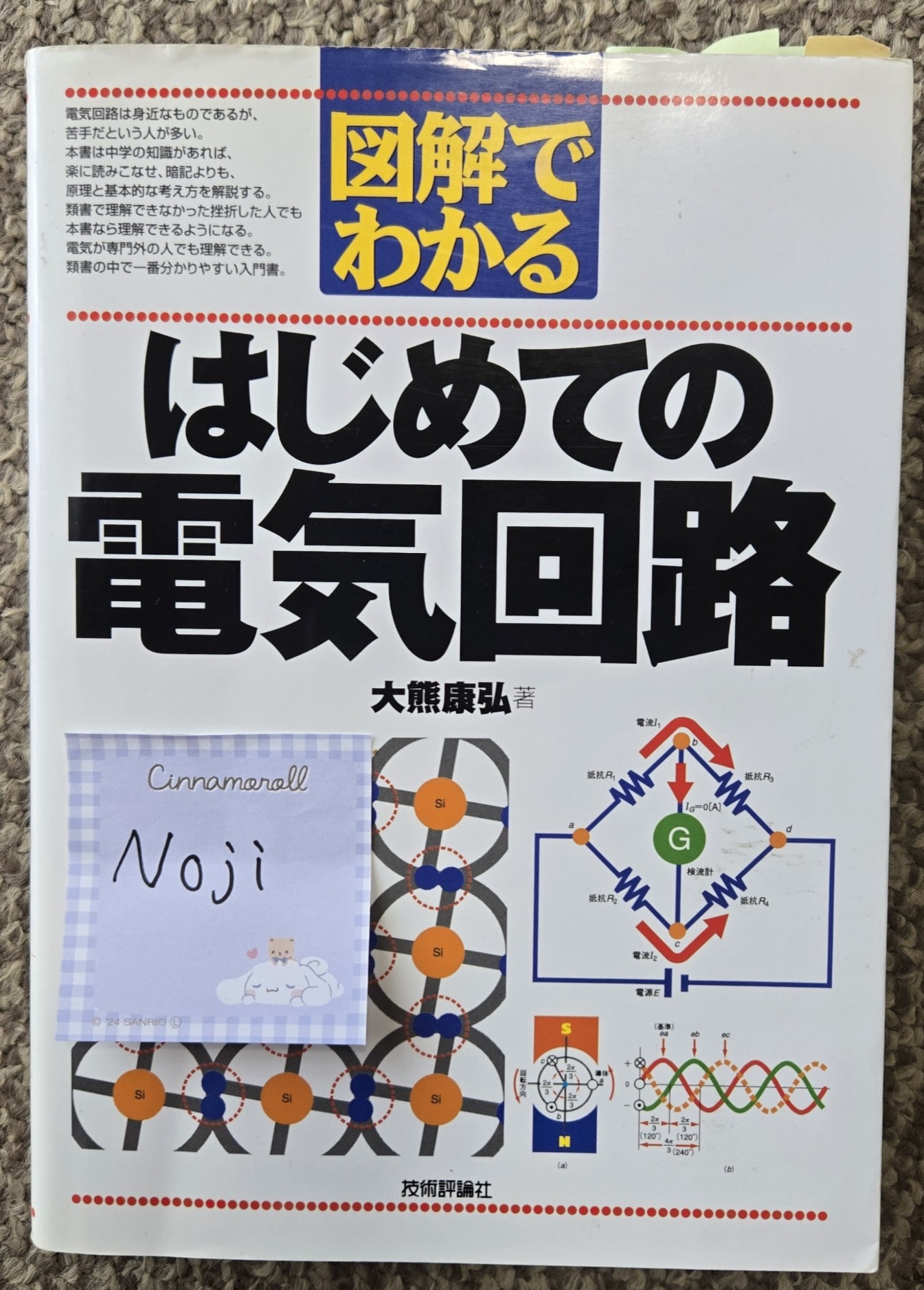
この本は、私が社会人1年目、回路設計の部署に配属されたときに購入して勉強した本です。
現在は改訂版が出ており、表紙も変わっています。
本屋さんで立ち読みをしてみましたが、内容は変わっていませんでした。(全ページを確認したわけではないですが)
- 図解がたっぷりで、イメージが頭に浮かびやすい
- それでいて本文や数式の説明もあり、しっかり理論も学べる
- 簡単な確認問題(例題)もついていて、公式の使い方を練習できる
「読みやすさ」と「しっかり学べる感」のバランスが非常に良い一冊でした。
実務に入る前の導入書としても、電験三種の理論科目を始める前にも、どちらの立場にもフィットします。
ただし、あくまで入門書なので──
- 過去問が解けるようになるレベルではない
- 回路設計がすぐにできるようになる本でもない
とはいえ、「電気の基礎とイメージを掴む」にはベストな一冊です。
📘 カラー徹底図解 基本からわかる電気回路|図解を眺めるだけでも頭に入る!
この本も、書店でじっくり読んで「これは初心者にすごく良いな」と感じた一冊です。
- タイトル通り図解がフルカラーで見やすく、飽きずに読める
- 内容は前述の書籍と似ていますが、こちらのほうが**「読む」要素が多め**
- 確認問題はないので、あくまで“読み物”として理解を深める使い方がおすすめ
「まずはさらっと通読して、全体像を掴みたい」
「がっつり勉強する前に、“電気ってこういう世界なんだな”と感じておきたい」
という方にはピッタリです。
✅ まとめ:試験勉強にも実務にも“基礎やイメージ”が大事
私自身、「理系なのに電気が分からなかった人間」でした。
だからこそ、基礎をしっかりイメージで理解できることが、どれだけ後々の勉強や実務を楽にしてくれるかを身をもって感じています。
これから電験三種に挑戦する方も、仕事で電気回路に関わることになった方も、まずは図解で学べる「電気の入口」に立ってみることをおすすめします。
😰 独学が不安な方へ
ここまで読んでくださった方の中には、こんなふうに感じている方もいるかもしれません。
「独学だけで本当に合格できるのかな…?」
「参考書を読んでも理解できる気がしない…」
その気持ち、すごくよくわかります。
私自身、最初は何をどう勉強すればいいのか分からずに悩んだ経験があるので、“入口での不安”って本当に大きいんですよね。
最近では、電気の基礎から丁寧に教えてくれる通信講座も増えてきました。
電験三種に特化して、初学者がつまずきやすいポイントをしっかりフォローしてくれるので、独学よりも圧倒的に効率的に進められるケースもあります。
✅ 通信講座を使うメリットとは?
- 試験に出やすい範囲に絞ったカリキュラムで、最短ルートで合格を目指せる
- プロ講師の解説動画で、難しい概念もスッと理解できる
- 質問サポート・添削対応ありで、疑問をそのままにしない
- 参考書や問題集で迷わないから、悩む時間が減って勉強に集中できる
- スケジュール管理がしやすく、学習が習慣化しやすい
私の職場にも、電験三種を取得して入社してきた方がいます。
その方はモーターや電気回路の基礎をしっかり理解していて、特に理論面にかなり強く、新人でも即戦力として現場で活躍しています。
改めて、電験三種で得た知識は実務にも本当に役立つと感じました。
「独学では厳しいかも…」と感じている方にとって、通信講座は合格に向けた強力なサポートになります。
「確実に合格したい」
「最短で効率的に学びたい」
「電気の基礎から丁寧に学び直したい」
そんな方は、一度通信講座の内容もチェックしてみてください。