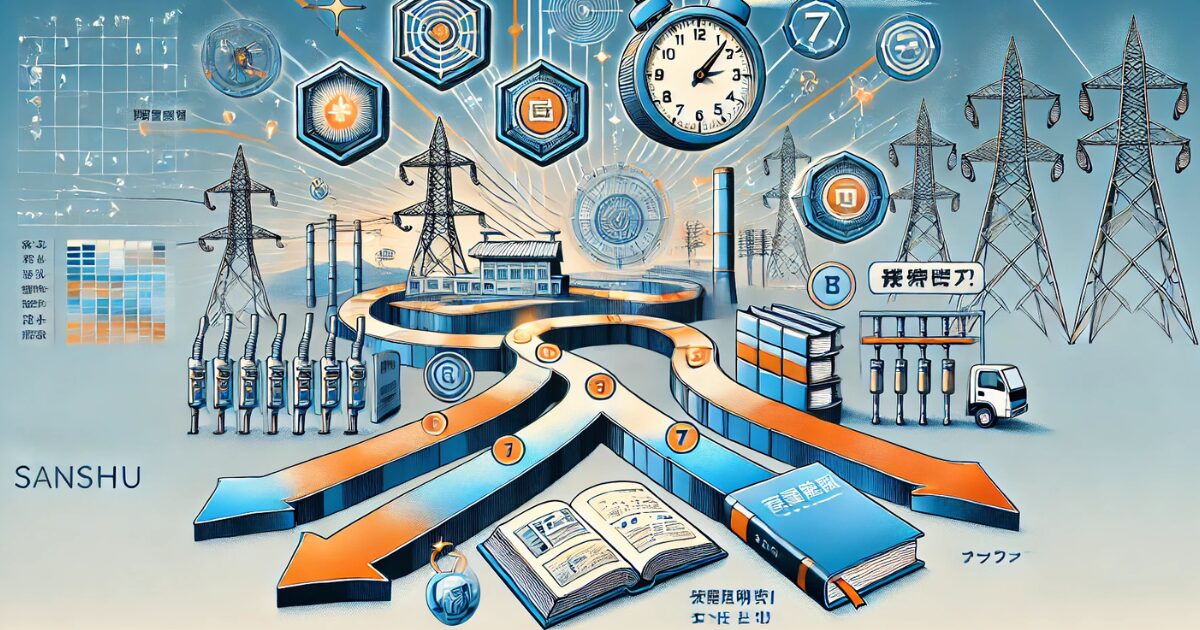「電験三種って難しそう」
「働きながら独学で合格は大変」
そんな不安を抱えている方に向けて、私が電験三種に一発合格した実体験をもとに、効率よく合格を目指せる勉強方法を7つ紹介します。
この記事では、電験三種の試験の特徴や、科目ごとの勉強の優先順位、実際に効果があった学習法など、「これから受験する人が最短距離で合格に近づくためのコツ」をわかりやすくまとめています。
私自身が実践して効果のあった勉強法や、学習した経験から得た気づきをもとに厳選しているので、きっと役立つはずです。
効率的な独学法を探している方や、勉強のやり方に迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
🔍 電験三種の特徴と難易度 ~効率的な勉強法を知る前に試験を理解しよう~
効率的な勉強法を知る前に電験三種について理解しておきましょう。
ここでは、以下の項目について簡単に解説します。
- 電験三種とは?
- 出題科目と試験形式
- 合格率と難易度
- 難易度の特徴
- 必要な勉強時間の目安
✅ 電験三種とは?
電験三種(第三種電気主任技術者試験)は、電気設備の保安・監督業務を行うために必要な国家資格です。
合格すれば、最大5万ボルト未満の電気設備の保守・管理が可能になり、電気業界では高い需要があります。
⚡ 出題科目と試験形式
電験三種は以下の4科目で構成されています。
- 理論:電気回路や電磁気学、計測などの基礎知識を問う科目
- 電力:発電・送電・配電・変電など電力系統に関する知識が中心
- 機械:電動機、変圧器、パワーエレクトロニクスなど機械系の出題
- 法規:電気事業法や電気設備技術基準など法規関連の暗記科目
試験は マークシート方式で、各科目100点満点中60点以上で合格となります。(試験の難易度により、合格点が引き下げられることもあります)
📈 合格率と難易度
電験三種は毎年約5万人が受験し、合格率は **約8~21%**と低めです。
膨大な勉強時間も必要とすることから難易度は高いと言えるでしょう。
4科目すべてに合格する必要がありますが、 科目合格制度があるため、一度合格した科目は翌々年度まで免除されます。
🔥 難易度の特徴
- 計算問題が多く、思考力が求められる
特に理論や機械は計算問題が頻出し、計算力と本質的な理解力が重要です。 - 範囲が広く、膨大な学習時間が必要
電験三種は4科目あり、それぞれの科目の範囲も広いです。その為、膨大な学習時間が必要になります。
⏰ 必要な勉強時間の目安
電験三種に合格するためには、一般的に約1000時間の勉強が必要だと言われています。
これは、1日3時間勉強すると仮定すると、約1年かかる計算になります。
ただし、これは目安の一つで、理系・文系のバックグラウンドや電気の知識があるかどうかによって必要な勉強時間は変わってきます。
💡 電験三種は戦略的な対策が鍵!
電験三種は難関資格ですが、試験の特徴を理解し、対策法を工夫することで効率よく合格を目指せます。
次章では、 電験三種に特化した効率的な勉強法 を具体的に解説します!
📈 効率的な勉強法 ~鉄損=銅損で最大効率を目指そう~
難関資格に合格するには、効率的な勉強法が必要不可欠です。
学習成果は、
勉強時間 × 効率
で決まります。
「何当たり前なこと言ってんだお前(笑)」
と思うかもしれませんが、単純計算で効率が2倍になれば、同じ成果を半分の時間で達成できます。
難関資格の勉強はどうしても長期間にわたるため、できるだけ効率よく学習し、必要な勉強時間を短縮したいですよね。
今回は、電験三種に特化した効率的な勉強法について、私が実際に勉強し、合格した体験談をもとにまとめました!
皆さんも変圧器の鉄損と銅損がイコールになるような最大効率で勉強して(笑)、合格を目指しましょう!
📚 合格への近道!効率的な各科目の学習の順番
- まずは理論から!
理論が理解できていないと、機械や電力の計算をスムーズに解くことが難しくなります。
そのため、最初に理論をしっかり固めることが重要です。 - 理論の次に機械または電力
理論を学んだ後に、機械や電力を学習すると理解しやすくなります。 - 最後に法規
計算問題が中心の他の科目と異なり、法規は暗記がメインのため、最後に取り組むと効率的です。
🔁 忘却のスパイラル!?4科目をバランスよく復習する重要性
復習の大切さは誰もが理解していると思いますが、電験三種は4科目あり、それぞれ範囲が広いため、特に意識して復習を行う必要があります。
- 1科目ずつ進めると忘れるリスクが高い
例えば、理論を一通り終えた後に機械、機械の後に電力…と進めると、最初に学習した理論の内容を忘れてしまう可能性があります。(実際に私自身がそうでした) - 「学んでもすぐに忘れる」スパイラルに陥る恐れ
ある科目をマスターしても、他の科目の内容を忘れてしまうといった状況に陥ることがあり、これが意外と厄介です。 - 4科目一発合格には「定期的な復習」と「各科目まんべんなく周回」が必須
各科目を少しずつ並行して復習しながら、知識を定着させることが重要です。
📝 合格者は必ずやっている!過去問を効果的に活用する工夫
令和5年度以降の電験三種では、過去問と類似した問題が頻出しています。
そのため、過去問対策は合格への最短ルートです。
単なる演習ではなく、過去問を徹底的に分析・活用することで合格率が大幅にアップします。
✅ ① 過去問は「傾向分析」と「対策」に最適
過去問は単なる問題練習ではなく、出題傾向を知るための最高の教材です。
- 頻出分野が分かる!
電力・機械では特定の分野から毎年出題される傾向があります。
特に四機(変圧器、直流機、誘導機、同期機)は高頻度で登場するため、重点的に対策すべきです。 - 難易度の感覚がつかめる!
本番の試験に近い問題に慣れることで、解答スピードや計算精度が向上します。
🔥 ② 効率的な過去問演習のコツ
過去問はただ解くだけでなく、効率的に活用する工夫が重要です。
- 🔁 繰り返し解く!
→ 1回解くだけで終わらせず、最低3周は解くのがおすすめです。
→ 2周目は「解法の流れ」を意識し、3周目は「時間内に解けるか」を確認しましょう。 - ⏱️ 時間を測って解く!
→ 本番同様の時間設定で演習することで、試験中のペース配分を体感できます。 - 📌 間違えた問題は解説を熟読!
→ 間違えた問題は苦手分野です。解説をしっかり読み込み、苦手分野や学習の不足分を補強しましょう。
→ 曖昧な部分やなかなか覚えられない内容はノートにまとめて復習すると効果的です。
📚 ③ 最新の過去問は本番シミュレーションに最適!
令和5年度以降は、過去問からの出題が多くなり、出題傾向が変化しています。
そのため、直近3年分の過去問は本番シミュレーション用として特に重視しましょう。
- 本番と同じ時間で解き、時間配分や緊張感に慣れる
- 実際に出題された問題形式や傾向に触れることで、本番への適応力が向上
💡 過去問対策で合格率アップ!
過去問は「使い方次第」で効果が倍増します!
単なる演習で終わらせずに、出題傾向を分析し、繰り返し解くことで得点力を強化しましょう!
✨ 本番で過去問と似た問題が出たときに、迷わず解けるようになります!
💡 丸暗記NG!本質を理解して得点力をアップ
電験三種の問題は本質を理解していないと解けないものが多く、公式や解法をそのまま暗記するだけでは本番の試験問題には対応できません。そのため、以下の点を意識して学習することが重要です。
【本質を理解することの重要性】
- 公式の意味や導出過程、原理を理解することで、応用問題にも対応できるようになる。
- 本番の試験で問題を見たときに、適切な解法や公式の変形が思い浮かぶようになる。
【過去問の暗記では限界がある】
- 最近の電験三種は過去問からの出題が多いと言われているが、20年以上前の問題が出ることもあるため、全てを暗記するのは現実的ではない。
- 問題の数値や選択肢の順番が変わることもあり、解答の丸暗記は難しい。
- 過去問演習は重要だが、それ以上に「本質を理解すること」が大事。
【公式・知識の暗記を最小限にする工夫】
- 必要最低限の公式だけ覚え、そこから導出できるようにすることで、暗記量を減らせる。
- 公式の意味や成り立ちを理解すれば、覚えやすくなる。
- 論説問題も「なぜそうなるのか?」を理解すれば、知識の丸暗記をせずに解答できる。
電験三種の学習では、単なる暗記ではなく「本質を理解すること」を意識することで、効率的かつ確実に合格を目指せるでしょう。
私は本質をしっかり理解したことで初見の問題にも対応でき、高得点で合格することができました。
本質を理解するのに役立ったのは、YouTubeチャンネル「電験合格」です!これなしでは一発合格はできなかったと思います。
⚠️ 完璧主義を捨てろ!理解は後からついてくる
電験三種は4科目あり、それぞれの範囲も広いため、「すべてを完璧に理解しよう」とすると学習がなかなか進みません。
そのため、以下のポイントを意識しながら進めることが重要です。
【理解度のバランスを意識する】
- 全く分からないまま進めるのは良くないが、ある程度理解できたら次に進むことも大切。
- 1つの問題にこだわりすぎて時間をかけすぎると、他の科目や分野の勉強が遅れてしまう。
【分からない部分は一旦「保留」にする】
- どうしても理解できない部分は深追いせずに、一旦保留して先に進むのも効果的。
- 学習を進めていく中で、他の分野や科目の知識とつながり、後から理解できることがある。
【学習を進めることで理解が深まる】
- 「最初は分からなかったけど、後から急に理解できた」という経験はよくある。
- 他の分野や科目の知識がヒントになり、理解が進むことがあるので、焦らずに学習を続けることが大切。
経験したことのある人は分かると思いますが、電験に限らず、他の分野の知識とつながって後から理解できることは良くありますよね!(あるあるですね)
学習は積み重ねなので、「分からないから進めない」ではなく、「とりあえず進める」ことも大事です。
最初は分からなくても、後からつながることが多いので、安心して学習を継続していきましょう!
🎯 4科目一発合格を狙え!
電験三種は4科目ありますが、忙しくて勉強時間を確保できない方は、科目合格を目指すのも一つの戦略です。
現在は年に2回試験があるため、1回の試験で1科目ずつ合格していけば、最終的に4科目合格することが可能です。
ただし、時間が確保できるなら4科目同時合格を目指すのがおすすめです。
理由は以下の通りです。
✅ 各科目の知識が重なる
- 同じ知識で解ける問題があるため、効率よく学習できる。
- 例:
- 揚水発電の問題、進相コンデンサ投入による力率改善の問題 → 電力と法規で出題
- パワーエレクトロニクスの問題(機械) → 理論で出題歴あり
- オペアンプの問題(理論) → 機械で出題歴あり
- 例:
✅ 知識がつながり、理解が深まる
- 各科目を並行して学習することで、それぞれの知識が関連し、より本質的な理解につながる。
🔥 効率重視!重要度の高い問題から優先的に攻略
電験三種の試験では、問題の難易度に関わらず全て同じ配点(※法規を除く)となっています。
これは電験三種の試験の大きな特徴だと思いました。
この特徴を利用し、難問を無理に解くよりも、基本的な問題と標準的な問題を確実に取ることが合格への近道です。
【試験の問題構成】
試験問題は、大きく以下の3種類に分けられます。
1️⃣ 基本的な問題 → 参考書通りの問題で短時間で解けるものが多い
2️⃣ 標準的な問題 → 多少の思考力が必要だが、対策していれば解ける
3️⃣ 難問・奇問(捨て問) → 見たことのない問題や、計算量が多く時間がかかる問題(二種レベルの問題が出題されることも)
【試験本番では、時間配分が非常に重要!】
- 基本的な問題は確実に得点!
- 標準的な問題もできる限り解く!
- 難問は飛ばし、最後に時間が余れば挑戦!
【対策すべき問題の優先順位】
試験勉強では、以下の順番で優先的に対策しましょう。
✅ 1番:よく出る & 簡単な問題(最優先!)
✅ 2番:よく出る & 難しい問題(できる限り対策)
✅ 3番:あまり出題されない & 簡単な問題(余裕があれば)
✅ 4番:あまり出題されない & 難しい問題(捨ててもOK)
4番:あまり出題されない&難しい問題」は、勉強しても試験で出題される可能性が低く、理解に時間がかかるわりに得点につながりにくいため、無理に対策する必要はありません。
最近は過去問そのままの問題も出題される傾向にあるので、どうせ捨てるなら答えだけ暗記しておくのも一つの手です。

✅ まとめ:最大効率で勉強して最短で合格を目指そう!
✅ ① 理論 → 電力 or 機械 → 法規の順番で学習を進めよう!
科目ごとの学習順は重要です。
最初に「理論」をマスターすると、後の電力・機械で必要な計算力や電気の基礎知識がスムーズに身につきます。
最後に「法規」を学習すれば、直前期にまとめて暗記できるため効率的です!
✅ ② 4科目バランスよく復習して、忘却のスパイラルを防ごう!
学習した内容は放置するとどんどん忘れてしまいます。
特に電験三種は4科目あって範囲が広いため、最初に学習した内容を忘れがちです。
復習を定期的に行うことで記憶が定着しやすくなります。
✅ ③ 過去問を効果的に活用しよう!
令和5年度以降は過去問からの出題が急増中!
そのため、過去問対策が合格への最短ルートです。
過去問を効果的に活用することで出題傾向に慣れ、本番での得点力がアップします!
✅ ④ 本質を理解して初見問題に対応できるようにしよう!
丸暗記ではなく公式や法則の成り立ちを理解することが大切です。
本質を理解することで、応用問題や初見問題にも柔軟に対応できます!
「なぜそうなるのか?」を意識して学習しましょう!
✅ ⑤ 完璧主義は捨てて学習を進めよう!
勉強していると理解できない箇所で手が止まってしまうことがありますが、そこで立ち止まるのは非効率です。
「今は分からなくても、後で理解できることもある」と割り切りましょう!
とりあえず先に進めることで知識がつながり、後からスッと理解できるケースも多いです。
完璧を目指さずに着実に前進することが合格への近道です!
✅ ⑥ できれば4科目一発合格を狙おう!
電験三種は科目ごとに出題範囲は異なりますが、同じ知識で解ける問題が多くあります。
科目間で知識がリンクすることで理解が深まるため、4科目同時に勉強する方が効率的です。
4科目一発合格を目指して、知識を横断的に活用しましょう!
✅ ⑦ 重要度の高い問題を優先して対策しよう!
全ての問題を網羅する必要はありません。
「頻出度」と「解きやすい問題」を優先的に対策するのが効率的です。
電験三種は配点が同じなので、頻出問題を重点的に対策しましょう!
電験三種は範囲が広く難関資格と言われますが、効率的な勉強法を実践すれば合格できます!
この記事で紹介した7つの勉強法を実践して、**効率よく合格を目指しましょう!**🔥