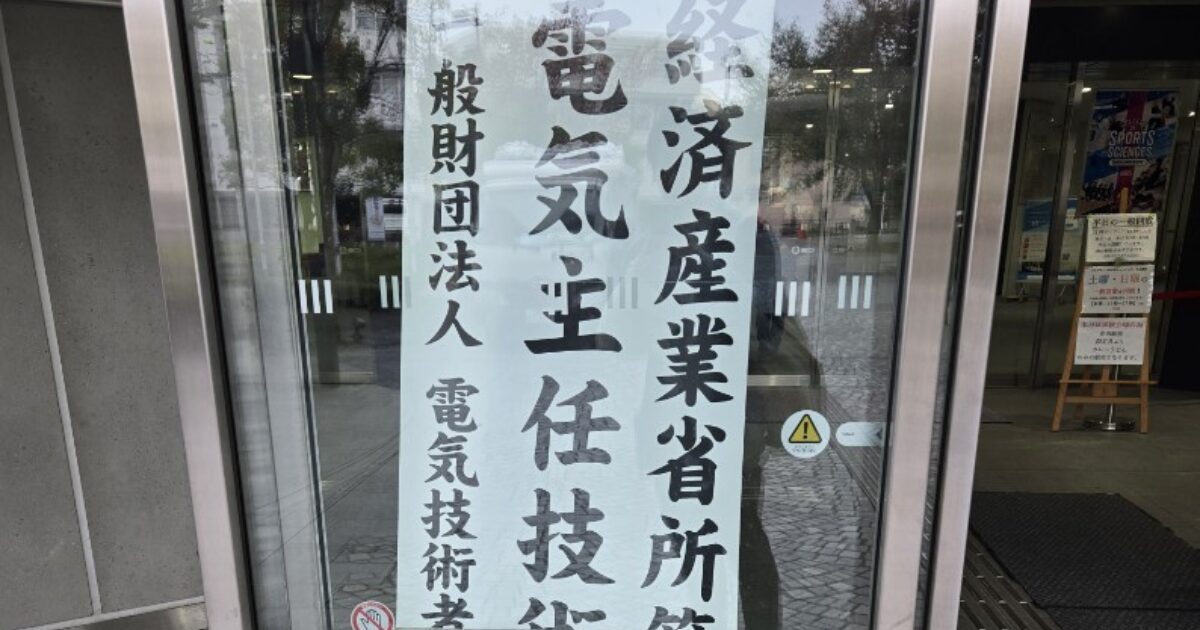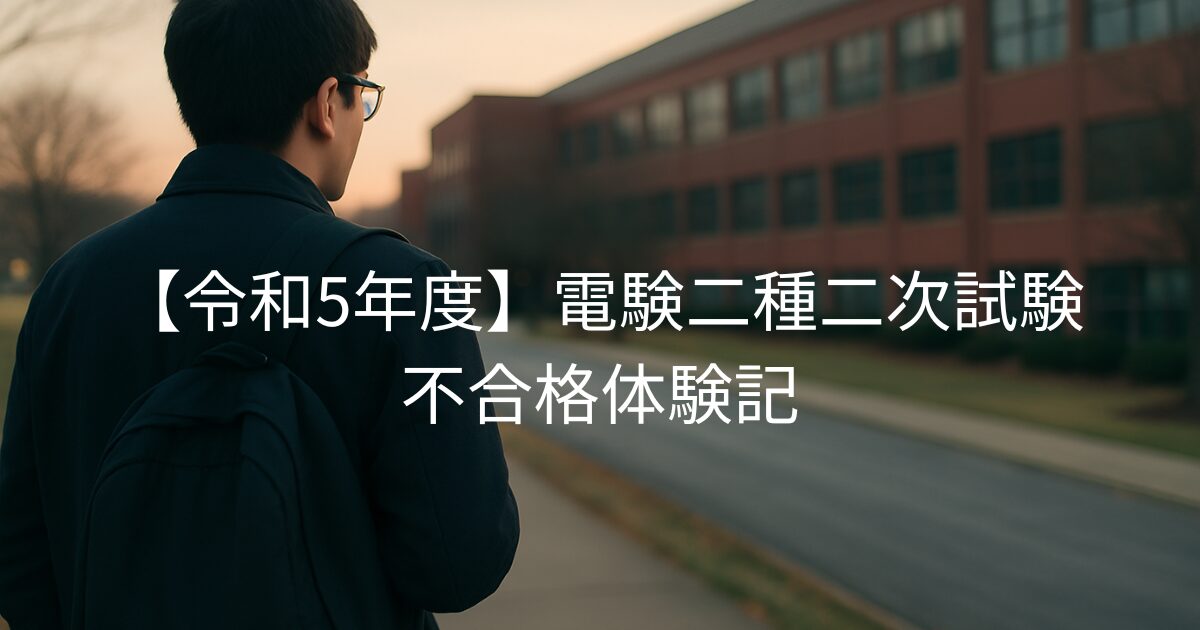「電験二種の二次試験って記述式みたいだけど、実際どんな感じなんだろう?」
「試験中の時間配分ってどんな感じ?」
そんな不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
私自身も受験前は、計算量や論述の分量に圧倒されそうになりながら、「時間内に書ききれるのか?」と不安でいっぱいでした。
しかし実際に受験してみてわかったのは、事前の戦略と時間感覚の把握がカギになるということです。
この記事では、私が令和6年度の二次試験を受けた体験をもとに、当日の雰囲気や緊張感、試験本番の流れ・時間配分・問題選択など、受験直前に知っておくと安心できるポイントを詳しく解説します。
本番で焦らず実力を発揮するためのヒントとして、ぜひ参考にしてください。
目次
起床から会場まで|試験当日の緊張と過ごし方
試験当日は朝6時に起床。
寝起きからすでに緊張で胸がざわざわしていました。
試験開始は10時でしたが、余裕を持って7時ごろには家を出発。
幸いにも会場までは電車で30分ほどと近く、8時過ぎには到着しました。
ただ、9時過ぎまでは建物の中に入れず、しばらく外で待機。
11月ということもあり、風が冷たくて寒かったです…。
他にも数名が外で待っていて、参考書を開いてラストチェックをしている人もいれば、スマホを見てリラックスしている人もいました。
自分はというと、1年間、本気で勉強してきた分、もうかなりの緊張状態。
参考書を開く気にもなれず、「この1年の努力が今日に詰まってる」と思うと、ドキドキしました。
そんな緊張を少しでも和らげるために、会場の庭をゆっくり歩きながらストレッチをしたり、会場に着くまでの間は心の中でSMAPの『SHAKE』を口ずさんでいました(ちょうどその時期、timeleszのオーディション番組でSHAKEが課題曲になっていて、妙に耳に残っていたんです)。
この"心の中カラオケ"が不思議と効果的で、少し気持ちがほぐれたのを覚えています。
あとは問題が解けなかったらどうしよう、とネガティブに考えるのではなく、どんな問題が出るか楽しみだ!俺が解けないはずがない!と思うと、自然とワクワクした気持ちにもなれました。

第1時限目【電力管理】(10:00~12:00)
試験問題は以下の6問から4問を選択します。(配点は各30点)
- 問1:【論説】汽力発電所の復水装置(復水器と復水器真空ポンプ)、脱気器の役割と仕組み
- 問2:【論説】油入変圧器の内部故障検出に使用される保護リレーについて
- 問3:【計算】一線地絡事故時の電磁誘導
- 問4:【計算】配電線のループ系統/短絡計算の複合問題
- 問5:【論説】ガス絶縁装置で扱うSF6ガスに関する問題
- 問6:【論説】分散型電源の大量連携時の課題について
※試験問題と解答は下記のリンク先から確認できます。
第二種電気主任技術者試験の問題と解答 | 第二種電気主任技術者 | 電気主任技術者 | 一般財団法人 電気技術者試験センター
問題選択(10:00~10:05)
試験開始の合図とともに全問題を確認します。
うわー、マジかよ、どれも難しそう、どうしよう。。。
論説が4問とも半分くらいは解答できそうだけど、完答は厳しそうな感じがしました。
計算は問3は解けそう、問4は難しそう、と感じました。
まずは問3を選択。残り3問は全て論説にするか、問4の計算をやるか迷いましたが、論説は完答が厳しそうだったので問4を一旦解いてみることにしました。
論説はどれも完答は難しいけど、問1と問6が自分は書きやすそうだと思いました。
問4は完答、論説は2問とも半分は部分点貰えるくらいは書けたので、この選択は正解でした。
問3(10:05~10:30)
小問は3問でした。
3問なので各10点でしょうか。
(2)は(1)の結果を、(3)は(2)の結果を使って解いていくタイプの問題でした。
私は対称座標法は捨てていましたが、(1)の一線地絡電流と零相電流の関係は直前に確認していたので、解けました。
直前に確認していなかったら、アウトでした。。。
問題分も「一線地絡電流を零相電流を用いて示せ」としか書いてないので、「地絡電流は零相電流の3倍になるので、」という文言を書いて答えをいきなり書きました。
公式解答では残念ながら導出過程もあったので、減点かもしれませんが、10点中マイナス5点程度では無いかと思っています。
(2)は(1)ができれば簡単に解ける問題でした。
しかし、答えに絶対値の記号を入れ忘れました(Xではけっこう入れ忘れている人が多かったです)。
この程度なら、10点中マイナス2点~5点程度では無いかと思います。
(3)は(2)の結果に問題分の数値を代入するだけなので、問題無く解けました(答えも合っていました)。
10分~15分程度で解ける問題だったと思いますが、計算ミスや考え方が間違っていないか念入りに確認した為、25分くらいかかってしまいました。
自己採点結果は30点中20点~25点くらいだと思います。
問4(10:30~11:10)
問4は(1)、(2)はただのループ系統の問題でしたが、問題文や条件が長く、送り出し電流という言葉が出てきたり、今までの過去問とは図や問題の系統が異なるタイプ問題だったので、最初解き方が分からなかったです。
良く考えたらループ系統の計算だと気づき、完全攻略などでやったループ系統の問題の解き方で解けました。
これに気づけるかどうか、と若干計算量も多かったので、けっこう出来なかった人も多かったんじゃないか、と思います。
(3)は典型的な短絡計算の問題で計算は多かったですが、解けました。
一見難しそうに見えましたが、完全攻略などの過去問をやっていれば解ける問題でした。
問題の系統が初めて見るタイプだったので、それに惑わされず、ただのループ系統の問題だと気づくか、問題文が理解できるかがカギだったかと思います。
そこに気づくまでに時間がかかったのと、若干計算量が多かったので、私は完答まで40分はかかりました。
公式解答と比較し、全て答えまで完答できていたので、記述面で減点があるかもしれないことを考えても自己採点結果は30点中25点~30点は取れていると思います。
問1(11:10~11:25)
小問は2問(各15点と仮定)でした。
(1)復水器の役割は「キーワードで覚える!」でしっかり暗記していたので、「キーワードで覚える!」の文章をそのまま書けました。
仕組みや復水器真空ポンプはキーワード、これだけ電力管理、完全攻略には載っていなかったので記載できませんでした。
文字数も150字程度も書けませんでしたが、知ってることだけでも何とか書きました。
細かい仕組みや復水器真空ポンプについて書けなかったんですが、復水器に関してはしっかり書けたと思うので、15点中7~8点程度は貰えてるんじゃないかと予測します。
(2)は脱気器の役割と仕組みについての問題で、まさか脱気器なんて出るとは思わなかったんですが、「キーワードで覚える!」に脱気器の役割と仕組みは簡単ですが書いてあったので、キーワードで覚える!の内容をそのまま書けました。
(2)の自己採点結果は15点中8~12点くらいだと予想し、(1)と(2)を合わせて、30点中15~20点くらいだと予想します。
問6(11:25~11:40)
問6も小問は2問(各15点と過程)でした。
(1)は系統電圧上昇を抑える為の調相設備の種類を2つ挙げて、その原理と長所・短所を答える問題だったので、しっかり書けました。
基本的な問題で頻出分野なので、これはできると思います。
しかし、(2)は全く知らない問題だったので、何とか考えて適当に書きました。
対象の事故事象は適当に電源脱落事故と書き、事故時運転継続の条件は、自分が知っている知識の中から事故が起きた時の影響を書きましたが、公式解答と比較すると問われていることに対する解答では無く的外れだったみたいです。
ただ、間違ったことは書いていないので、電力系統の知識を示せた点でワンチャン部分点くれる?
自己採点結果は(1)は15点中10~12点、(2)は15点中5~8点で合計30点中15~20点と予想しました。
見直し(11:40~12:00)
問4の計算問題にかなり時間を費やしましたが、論説問題が各15分程度で終わったので、時間は20分余り、全体の見直しの時間に使いました。
昼休み(12:00~13:20)
電力管理では最初に問題を見た時にぱっと見完答できそうな問題が無く、かなり集中して頭を使い考えたので、相当エネルギーを使いました。
電力管理が終わった時点でとても疲れて、頭も痛かったです。
試験中はかなり集中したからなのか、頭も痛くヒートアップしていて、喉も乾いていたので、たまたま近くにいた試験監督に声をかけてお茶を飲ませて貰いました。
試験中はペットボトルが机の上に置けないので、水分補給する場合は試験監督に声をかける必要がありますが、「恥ずかしいから」「めんどくさいから」といって我慢するのは良くありません。
最悪、体調を悪くして試験を受けられなくなるかもしれません。
令和6年度は電力管理のほうが難しかったので、周りも試験終了の合図とともに、「ハアー。。。」って感じの疲れた声が聞こえました。
午後の試験中にお腹痛くなると嫌なので(トイレが近いタイプなので)、昼ご飯は予めコンビニで買っておいたおにぎり2個だけ食べました。
また、体力回復の為、栄養ドリンクを飲み、お茶などで水分補給もしました。
午前の試験でかなり頭が疲れた為、昼休みや午後の試験に向けての最終チェックをする余裕はありませんでしたが、栄養ドリンクや水分補給をし、昼休みにしっかり休むことで、午後の試験に向けての体力回復ができました。
第2時限目【機械制御】(13:20~14:20)
試験問題は以下の4問から2問を選択します。(配点は各30点)
- 問1:【論説+計算】同期発電機の短絡比に関する論説と計算問題
- 問2:【計算】単相変圧器の無負荷試験と短絡試験
- 問3:【計算】降圧チョッパの計算問題
- 問4:【計算】ブロック線図から定常値や時間応答を求める問題
※試験問題と解答は下記のリンク先から確認できます。
第二種電気主任技術者試験の問題と解答 | 第二種電気主任技術者 | 電気主任技術者 | 一般財団法人 電気技術者試験センター
問題選択(13:20~13:25)
電力管理とは逆に問題を見た瞬間、「きた!」と思いましたね(笑)
問2は過去問とほぼ同じだったので見たことある!
問1も後半の計算は基本的な問題で、問4の自動制御もわりと典型的な問題?だったので、これは行ける!と思いました。
パワエレは捨てているので問3は除外。
問2は迷わず選択。
問1は機械制御にしては珍しく論説が混じっていたので、問4と迷いました。
問1は計算問題がかなり簡単だったので、問4も解けそうではありましたが、自動制御は計算に時間かかるので、最後まで解き切る自信が無かった為、問1を選択しました。
問1に論説が混じっていたので、問4を選択した人も多かったんじゃないか、と思いますが、問4はけっこう難易度が高かったらしく、この選択は正解でした。
問2(13:25~13:50)
過去問とほぼ同じ問題(数値違い)なので、真っ先に解きました。
計算量も少なく簡単な問題ですが、求めるパラメータが多いのと、あまりに簡単すぎて計算ミスなどしていないか不安で何度も見直しながら解いた為、難易度の割に時間がかかりました。
公式解答と比較して、答えも全て合っていたので、完答でした。
ただ、問題文に電圧変動率の式が与えられていて、力率がcosφと定義されていましたが、cosθと書いたかもしれなく、減点の可能性があります。
まあ、大きくは減点はされないでしょう。
自己採点の結果は30点中25~28点と予想します。
問1(13:50~14:10)
(1)の論説は短絡比の定義に関する問題で、機械制御は論説の対策はしていないですが、基本的な内容(三種レベル)なので、普通に書けました。
無負荷飽和曲線と三相短絡曲線を得る試験方法は問題なく書けたと思います。
短絡比の定義が公式解答とは少し違う部分がありましたが、間違ったことは書いていないので、それなりに点数は貰えたかと思います。
(2)の計算問題は非常に簡単で単位法が出てきましたが、計算量も少ないので完答できました(公式解答と答えも一致)。
問1は論説が混じっていたのと、(2)の計算が簡単だったので、時間もそこまでかかりませんでした。
自己採点の結果は、(1)が15点中10~13点、(2)が15点満点で、30点中25~28点と予想します。
見直し(14:10~14:20)
2問解き終えた時点で残り10分でした。
本番では途中で何回も見直したとは言え、今回の問題は比較的簡単だったのに、時間に余裕はあまりありませんでした。
問4の自動制御を選択していたら確実に終わっていなかったと思います。
機械制御は本当に時間が足りないです。
試験終了~帰宅
令和6年度の機械制御は比較的易しかったと思います。
電力管理とは違い、試験終了の合図とともに、周りから「よしー!」という声が聞こえてきました(笑)
機械制御はほぼ完答、電力管理もそれなりに手ごたえがありましたので、力は充分出し切ったし、大丈夫だろう、と思いました。
一つ不安だったのが、機械制御のほうは最後に解答用紙の問題番号を見直すのを忘れていたくらいです。
問題番号を書かなかったり、違う番号を書いていたら採点されないみたいなので、合格発表まではこれが一番不安でした(笑)
あとは、不合格になる可能性としては電力管理のほうが論説問題で部分点があまり貰えてなくて、平均点を下回ってしまう、というくらいですが、令和6年度の電力管理はけっこう難しい印象があったので、平均点は半分もいっていないんじゃないか、と思っています。
試験終了し、そのまま家に帰宅しました。
ひとまず試験が終わってホッとしました。
二次試験は一次試験と違って早く終わるのにかなり疲れましたね。
次の日仕事だったのに、試験のことが気になり、ずっとXで電験二種のポストを見ていたら、23時くらいになっていました。。。
試験結果(自己採点)
令和6年度の私の試験結果は公式解答と比較し、自己採点した結果は下記の通りです。
⚡ 電力管理
- 問1(論説):15~20点
- 問3(計算):20~25点
- 問4(計算):25~30点
- 問6(論説):15~20点
▶ 合計: 75~95点/120点(62%~79%)
⚙️ 機械制御
- 問1(論説+計算):25~28点
- 問2(計算):25~28点
▶ 合計:50~56点/60点(83%~93%)
🧮 総合計
125~151/180点(69%~83%)
※合格基準:108点(60%)かつ各科目平均点以上
けっこう余裕を持って合格できたんじゃないか、と思います。
ちなみに令和5年度は2割くらいしかできなかったと思います(笑)
令和5年度の不合格体験記はこちら👇
所感:電験二種二次試験を受験してみて感じたこと
ここでは実際に電験二種二次試験を受験してみて感じたリアルな本音を語ります。
- 当日の疲れや緊張感
- 問題選択、時間配分
- 最後まで諦めない心と落ち着いて集中すること
当日の疲れ、緊張は想像以上
試験当日、会場に向かう道中や開始までの待ち時間は、かなり緊張しました。
令和5年度の二次試験は「とりあえず受けてみよう」という気持ちだったので、肩の力が抜けていて緊張はほとんどしませんでした。
しかし、令和6年度の試験は1年間必死に勉強してきた分、「この1日にすべてがかかっている」と思うと自然と身が引き締まりました。
また、電験二種の二次試験は見たことのない問題が平然と出題されるため、試験中はかなり集中力を使います。
3時間という時間は決して長くはないものの、終わった頃には相当な疲労感がありました。
問題選択、時間配分が合否を分ける
今回の試験では、自分の問題選択は正しかったと感じています。
そのおかげで最後まで解き切ることができました。
もし問題選びや時間配分を誤っていたら、時間が足りなくなって解けるはずの問題を落としてしまい、悔いが残る結果になっていたかもしれません。
ですが、今回は自分なりに冷静に取捨選択し、時間を意識して進められたことで、実力をしっかり発揮できたと思います。
その結果には満足しています。
最後まで諦めない心(落ち着いてよく考え集中する)
電験二種の二次試験は問題数が少なく、見たことのない問題が出ることも珍しくありません。
私にとって今回の試験は、不合格なら一次試験からやり直しになる状況だったため、かなり気合を入れて勉強しました。
それでも、試験本番で電力管理の問題を見たときは、「完答できそうな問題がない」と感じて焦りました。
どの問題を選ぶか迷いましたが、特に問4の計算問題は最初はさっぱり分からず…。
それでも諦めずに冷静に考え直し、集中して解き進めた結果、最後には完答することができました。
実際には、勉強した知識で解ける問題が多かったのですが、試験本番ではその場のコンディションや運にも左右される部分があります。
それだけに、焦らず落ち着いて取り組むことがいかに大切かを改めて実感しました。
きっと今回、不合格になった方の中には、実力は十分にありながらも本番でうまく力を出し切れなかった方もいたのではないかと思います。
最後に(受験生へのメッセージ)
電験二種の二次試験は、これまでの人生で一番勉強した試験だったと思います。
だからこそ、当日の緊張や疲労感は想像以上でした。
趣味で受験したはずなのに、「もう二度とこんなキツい試験は受けたくない!」と心から思いました(笑)。
ただ、その分やりがいや合格した時の達成感は半端なかったです。
試験後は一気に気が抜けて解放された感じがしました。
自己採点では自信がありましたが、記述式で採点が明確でないので、合格発表までは不安でした。
合格を知った時はこれまでの努力が報われたという喜びは何にも代えがたいものでした。
これから二次試験に挑む皆さんも、当日は相当な緊張や疲労を味わうと思いますが、それ以上にやりがいや、合格した時の大きな達成感も是非味わってほしいです!
どうか最後まで自分を信じて、悔いのないよう全力を尽くしてください!
応援しています!