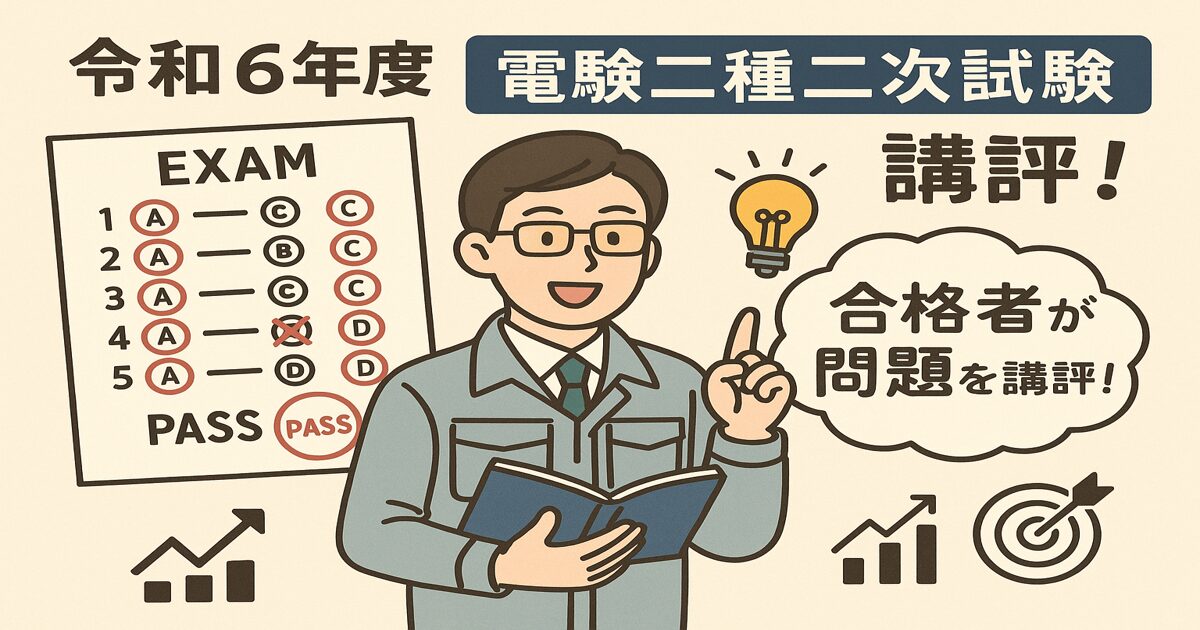私は令和6年度の電験二種二次試験を受験し、無事、合格しました。
実際に令和6年度の二次試験を受験した経験と複数の問題集をまんべんなく学習した経験から、試験問題の感想や難易度について講評し、どのような勉強、対策をすれば合格できる試験だったか考察してみました。
この記事がこれから電験二種を目指す人の参考になればうれしいです!
目次
⚡️ 電力管理
📄 試験問題
- 問1:【論説】汽力発電所の復水装置(復水器と復水器真空ポンプ)、脱気器の役割と仕組み
- 問2:【論説】油入変圧器の内部故障検出に使用される保護リレーについて
- 問3:【計算】一線地絡事故時の電磁誘導
- 問4:【計算】配電線のループ系統/短絡計算の複合問題
- 問5:【論説】ガス絶縁装置で扱うSF6ガスに関する問題
- 問6:【論説】分散型電源の大量連携時の課題について
※試験問題と解答は下記のリンク先から確認できます。
第二種電気主任技術者試験の問題と解答 | 第二種電気主任技術者 | 電気主任技術者 | 一般財団法人 電気技術者試験センター
🔥 問1:火力発電(論説)
汽力発電所の復水装置(復水器と復水器真空ポンプ)、脱気器について、その役割と仕組みを求める問題でした。
私は電気書院の「これだけ電力管理(論説編)」と「キーワードで覚える!」、オーム社の「完全攻略」の全ての問題(重複した問題を除く)を学習しましたが、復水器に関しては「キーワードで覚える!」にしか記載が無く、復水器真空ポンプについてはどの参考書にも記載がありませんでした。
脱気器についても「キーワードで覚える!」にしか記載が無く、役割や仕組みも簡単にしか書いてありませんでした。
私はこの問題を選択しましたが、復水器と脱気器に関しては「キーワードで覚える!」の内容をそのまま書けました。
同じ平成12年問題2でもキーワードほうはアレンジされていて、脱気器も載っていました。
完全攻略は過去問そのままなので載ってないです。
復水器に関しては基本的な内容ですが、問1は完全攻略(新制度の過去問)の問題を全て暗記しても解答するのは難しく、電験二種の参考書には載っていないような内容も出題された為、専門書を隅々まで読んでいる人や実務経験が無いと完答するの難しいんじゃないか、と思いました。
🏭 問2:変電(論説)
油入変圧器の内部故障検出に用いられる保護リレーに関する論説問題でした。
こちらも「これだけ電力管理(論説編)」や「完全攻略(新制度の過去問)」には記載がなく、「キーワードで覚える!(旧制度の過去問)」に比率作動継電器やブッフホルツ継電器、衝撃圧力継電器に関しては記載がありました。
しかし、励磁突入電流の話や地震リレーの話は載っていなく、私は「キーワードで覚える!」に載っていたブッフホルツと衝撃圧力しか分からなかった為、選択しませんでした。
一種令和元年度電力管理問2に類題があったみたいですが、二種の参考書にもあまり記載のない内容だったので難易度は高かったんじゃないか、と思います。
🛤️ 問3:送電(計算)
一線地絡事故時の電磁誘導に関する計算問題でした。
平成9年度問3の類題ですが、平成9年度問3では起誘導電流が与えられているのに対し、今回の問題は(1)で地絡電流(起誘導電流)を零相電流で示す必要がありました。
しかし、これは平成18年度問3ができれば問題なく解答できる為、「完全攻略」などで新制度の過去問をやっていれば容易に解ける問題でした。
計算量も少ないので、この問題は完答できる必要があります。
従って、難易度は易しいでしょう。
私は対称座標法については捨てていましたが、試験直前に地絡電流(起誘導電流)と零相電流の関係だけは抑えたので、解答できました。公式解答では導出過程まで書いてありましたが、(1)で地絡電流を零相電流を用いて示せないと、(2)以降の問題がアウトになっていましたので、直前に抑えておいて良かったです。
🏠 問4:配電(計算)
(1)と(2)は配電線のループ系統の問題、(3)は三相短絡電流を求める問題で、ループ系統と短絡計算を複合した珍しい問題でした。
問題文や条件が長く、過去問のループ系統の問題と図が異なったり、送り出し電流という言葉が出てきて、戸惑った人も多かったのではないかと思います。
私も最初は送り出し電流って何?何を求めればいいの?と思いましたが、落ち着いて良く考えればただのループ系統の計算問題と気づきました。
(3)は同図を用いた典型的な短絡計算の問題だったので、計算量はやや多いですが、難しくないと思います。
一見難しそうに見えましたが、実際は完全攻略(新制度の過去問)のループ系統や短絡計算の問題が解ければ、その知識で解ける問題だったので、難易度は標準だと思います。
🔌 問5:変電(論説)
ガス絶縁開閉装置に使用されるSF6ガスに関する論説問題でした。
(1)はガス絶縁に影響を及ぼす項目や管理方法は「これだけ電力管理(論説編)」、「完全攻略(新制度の過去問)」、「キーワードで覚える!」には記載が無く、(2)の温室効果ガスの話はキーワードで覚える!に記載がありました。
全体的に参考書に載っていないような内容が多く、難易度は高いと思います。
🛠️ 問6:変電、施設管理(論説)
(1)は調相設備に関する問題、(2)は分散型電源の系統への連携時求められる事故時運転継続の要件に関する問題でした。
(1)は系統電圧上昇を抑える為の調相設備の原理と長所・短所を求める基本的な問題で、「完全攻略」や「キーワードで覚える!」にも調相設備に関する問題はありますので、勉強していれば解ける問題でした。
(2)は今まで類題が無く、「完全攻略」や「キーワードで覚える!」に記載の無い難易度の高い問題だと思います。
試験後に気づきましたが、事故時運転継続の要件については「これだけ電力管理(論説編)」の本文中にさらっと書いてありました。
⚙️ 機械制御
📄 試験問題
- 問1:【論説+計算】同期発電機の短絡比に関する論説と計算問題
- 問2:【計算】単相変圧器の無負荷試験と短絡試験
- 問3:【計算】降圧チョッパの計算問題
- 問4:【計算】ブロック線図から定常値や時間応答を求める問題
※試験問題と解答は下記のリンク先から確認できます。
第二種電気主任技術者試験の問題と解答 | 第二種電気主任技術者 | 電気主任技術者 | 一般財団法人 電気技術者試験センター
⚙️ 問1:同期機(論説+計算)
機械制御では珍しく論説が混じっていたので、選択しなかった人も多かったのではないでしょうか。
しかし(1)の論説は短絡比に関する基本的な内容で、私は機械制御の論説は未対策でしたが、無負荷飽和曲線や三相短絡曲線、短絡比の定義は三種で勉強する内容ですので、論説といっても比較的簡単な部類の問題だったと思います。
(2)の計算は単位法が出てくるものの基本的な問題で、計算量も少なく難易度的に三種と大差ない容易に解ける問題でした。
🔌 問2:変圧器(計算)
平成28年問2とほぼ全く同じ問題であり、計算も簡単な為、確実に完答する必要がある問題でした。
💡 問3:パワーエレクトロニクス(計算)
私はパワーエレクトロ二クスは未対策だったので、問題の難易度は判断できませんが、例年難易度の高いパワーエレクトロニクスにしては比較的易しい問題だったようです。
📊 問4:自動制御(計算)
「完全攻略」などの新制度の過去問を解ければある程度解ける問題だと思いますが、自動制御は計算量も多く、問1、問2に比べると難しいと思います。
📋 私の試験結果(自己採点)
私が選択した問題と自己採点した結果は下記の通りです。
⚡ 電力管理
- 問1(論説):15~20点
- 問3(計算):20~25点
- 問4(計算):25~30点
- 問6(論説):15~20点
▶ 合計: 75~95点/120点(62%~79%)
⚙️ 機械制御
- 問1(論説+計算):25~28点
- 問2(計算):25~28点
▶ 合計:50~56点/60点(83%~93%)
🧮 総合計
125~151/180点(69%~83%)
※合格基準:108点(60%)かつ各科目平均点以上
✅ まとめ
この記事では各問題毎の難易度や傾向、過去問との関連性について講評しました。
最後にそれぞれの科目の難易度と必要な対策をまとめておきます。
⚡ 電力管理
- 問1:火力発電(論説) 標準
- 問2:変電(論説) 難
- 問3:送電(計算) 易
- 問4:配電(計算) 標準
- 問5:変電(論説) 難
- 問6:変電、施設管理(論説) 標準~やや難
令和6年度の電力管理は論説が4問で難易度が高く、計算は易しい年だったと思います。
論説は新制度の過去問を抑えるだけでは解答できず、「キーワードで覚える!」をまんべんなくやらないと解答は難しいと思いました。
計算は逆に「完全攻略」などで新制度の過去問をマスターすれば解ける問題でした。
⚙️ 機械制御
- 問1:同期機(論説+計算) やや易
- 問2:変圧器(計算) 易
- 問3:パワーエレクトロニクス(計算) ※未対策の為、講評無し
- 問4:自動制御(計算) やや難
問1、問2の計算は「完全攻略」などの新制度の過去問が解ければ容易に解ける問題でした。
問4の自動制御はやや難しい印象がありましたが、これも「完全攻略」の過去問を勉強すればある程度は解けるレベルではないかと思います。
📌 必要な対策について
令和6年度の二次試験は、論説が難しく、計算が比較的易しい年でした。
私自身、この試験に挑戦するにあたり、複数の参考書を幅広く学習しました。
その経験を踏まえ、令和6年度の試験で合格するために必要だった対策をお伝えします。
🧠 論説は「キーワードで覚える!」を徹底する
論説問題は過去問の類題が少なく、新制度の過去問を暗記するだけでは厳しいと感じました。
「キーワードで覚える!」で幅広い知識を網羅的に覚えることが重要です。
🔢 計算は「完全攻略」で十分対応可能
一方で計算問題は比較的シンプルで、「完全攻略」の新制度対応の過去問をマスターしていれば十分に対処できるレベルでした。
逆に言えば、基本的な計算パターンをしっかり押さえておけば、得点源にできる年だったと言えます。
✅ 年度ごとの傾向を意識した対策を!
今回の試験は計算が易しく論説が難しい年でしたが、年度によって難易度や出題傾向は変わります。
この対策はあくまで令和6年度向けである点にはご注意ください。
過去問や模試を通じて、その年ごとの傾向を見極めながら柔軟に対策を立てることが重要です。