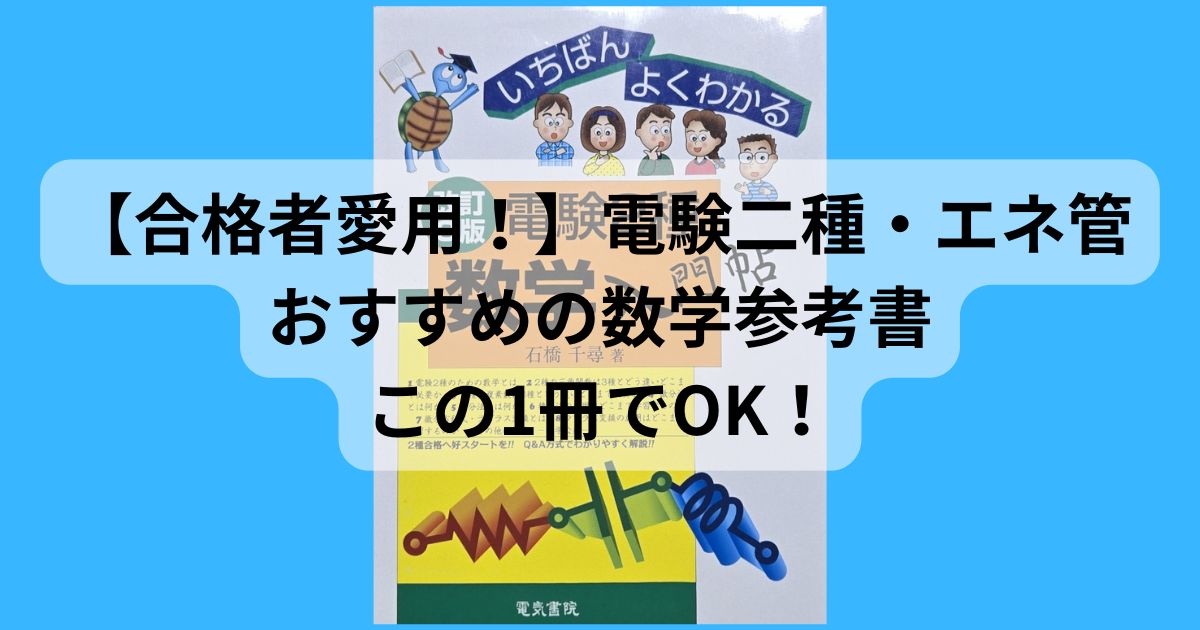電験二種・エネルギー管理士(電気)の数学、何から手をつければいい?
電験三種にはなかったラプラス変換や微積、三角関数の加法定理…。
「公式は見たことあるけど、実はよく分かってない…」と感じていませんか?
私もまさにそんな状態からのスタートでした。
特に社会人になってから勉強を再開すると、数学の基礎がごっそり抜けていて焦る場面が多々あります。
そんな時、私の助けになったのが、今回ご紹介する
👉 電気書院『いちばんよくわかる 電験2種数学入門帖 改訂3版』です。
電験二種に必要な数学だけに特化しており、
しかも単なる数学の参考書ではなく、「試験でどう使うか」まで分かる構成になっています。
この記事では、この本の内容やおすすめポイント、実際にどんな場面で役に立ったかを、合格者の体験をもとに詳しくご紹介します。
目次
📘 結論:電験二種・エネルギー管理士の数学はこの1冊でOK!
いきなり結論からいきますね。
電験二種やエネルギー管理士(電気)の数学対策で私が使って本当に役に立った参考書は以下の本です👇
電験三種からステップアップする際、多くの方がつまずくのが**ラプラス変換・微分積分・三角関数の加法定理などの「新たな数学」**です。
私自身も「電験三種ではなんとか乗り切れたけど、二種やエネ管では通用しないな」と痛感しました。
実際、数学が得意じゃない方にとっては、公式の意味や使いどころがわからないことが大きな壁になります。
ただ、逆に言えば、そこをしっかり理解すれば大きなアドバンテージにもなります。
この本はそんな「数学の基礎と試験での実践をつなぐ」役割を果たしてくれる一冊でした。
📖 内容紹介
ここでは、私の実体験ベースで以下の内容を紹介します👇
- この本で学べる内容
- 本書の特徴と構成
- 私の使い方と活用シーン
- おすすめポイント
📚 この本で学べる内容は?
「いちばんよくわかる 電験2種数学入門帖」では、電験三種の知識がある人を想定して、電験二種に必要な数学を丁寧に解説しています。
具体的には、以下のような内容が網羅されています👇
- 電験三種と二種で必要になる数学の違い(より発展的な内容にフォーカス)
- 三角関数(加法定理など)、複素数(共役・ベクトルオペレータ)などの拡張内容
- 微分法:基本から指数・対数・三角関数の微分、合成関数など
- 積分法:不定積分・定積分・部分積分・置換積分など
- 微分方程式とラプラス変換
- 応用編として、電験二種での使い方(回路や制御など)もカバー
- その他:行列、四端子定数など
「広く浅く」ではなく、**「試験に出る内容にピンポイントで深く」**がこの本の魅力です。
🔍 本書の特徴と構成
実際に使ってみて感じたこの本の強みは以下の通りです👇
🧩 特徴・構成
- Q&A形式の解説でつまずきやすいポイントを優しくフォロー
- 例題と確認問題で「分かったつもり」を防ぐ
- 章末の要点整理が公式の確認に便利
- 基本問題(数学問題) → 応用問題(電気回路の問題)の流れで、段階的に力がつく
🎯 応用問題も実践的!
応用問題が電験二種で実際に出題される形式の問題なので、数学の知識がどう使われるかがリアルに理解できます。
✍️ 私の使い方と活用シーン
正直、私はこの本を最初から全部やったわけではありません。
「困ったときの辞書的な存在」として使っていました。
✅ 私の活用法
- ラプラス変換が完全に抜け落ちていたので、一度この本でしっかり復習。その後、エネ管の「自動制御」の問題演習に入った。
- 電験二種・エネ管の勉強中に、微積や三角関数の公式を忘れてしまった時に辞書代わりに使った。
「必要なところだけ読む」使い方でも十分効果を感じました!
📌 おすすめポイント4選
私が実際に使用して感じたおすすめポイントは以下の4つです👇
- 電験二種に必要な数学に絞って解説している
- 微分とは?積分とは?ラプラス変換は何の為にやっているのか?など根本的な部分から丁寧に説明してくれる
- 電験二種用だがエネ管(電気)の勉強にも使える
- 単なる数学の本ではなく、電験二種にどう応用するかという視点で書かれている。
🧑🏫 【実体験】この本が役立ったシーン
ここでは私が電験二種やエネ管の勉強時にこの本が役立ったシーンを紹介します。
役立った分野は以下の3つです👇
- ラプラス変換
- 微分積分
- 三角関数
🔁 ラプラス変換:完全に忘れていても一から理解できた
私は大学でラプラス変換を学びましたが、卒業してから10年以上経って完全に記憶から消えていました。
「S?部分分数展開?確かにやったなあ」と思い出しました(笑)
エネ管の自動制御の問題で完全に詰まり、「これはまずい」と思って手に取ったのがこの本でした。
この本の第7章と第8章をじっくり読み込み、例題や章末問題も一通り解いて、
- ラプラス変換の目的やイメージ
- 逆ラプラス変換
- 初期値定理・最終値の定理の使い方
- 部分分数展開のやり方と意味
などを理屈ごと理解できました。
大学時代では公式や解き方を暗記していただけで、ラプラス変換や部分分数展開は何の為にやっているのかサッパリでしたが、この本で根本から理解できました。
おかげで自動制御の応答計算や定常値計算がスムーズになり、電験二種の二次試験にも大きく役立ちました。
📈 微分積分:必要な時にすぐに調べられた
高校や大学で習ったはずの微積分も、年月が経つとかなり忘れますよね。
私自身も電験二種の問題を解いている時に、
- 「あれ?合成関数の微分ってどうやるんだっけ?」
- 「部分積分の公式ってなんだっけ?」
という場面が何度もありました。
この本は例題と図解で丁寧に解説してくれていたので、すぐに理解を取り戻せて、ストレスなく問題演習に集中できました。
📐 三角関数:公式をスムーズに暗記&活用
電験二種の二次試験では、電験三種ではあまり出ない加法定理などの三角関数の公式が必要になります。
特に同期機の問題でよく出てきました。
この本には公式の導出や使い方の説明があり、単なる丸暗記ではなく使える知識として定着できました。
📕 【補足紹介】その他電験二種用数学参考書
私自身は使用していませんが、以下の参考書も有名なようです👇
気になる方はチェックしてみてください。
📘 「電験二種」合格の数学
📕 電験2種電気数学: 第3種から第2種へ
📙 完全マスター電験二種受験テキスト 電気数学
✅ まとめ:数学が不安な方こそ手に取ってほしい一冊
「いちばんよくわかる 電験2種数学入門帖」は、電験二種やエネ管の勉強をしていて、
- 「あれ?これどうやるんだっけ…」
- 「ラプラス変換って何のためにあるの?」
- 「数学が足を引っ張ってる気がする…」
と感じたことのある方に、ぜひおすすめしたい一冊です。
必要なところだけ読んでもOK。
辞書代わりにもなるし、通読して理解を深めることもできます。
「数学の壁を感じたらこの本を開く」
そんな一冊として、きっとあなたの勉強の支えになるはずです。
詳細はこちら👇
いちばんよくわかる 電験2種数学入門帖 改訂3版