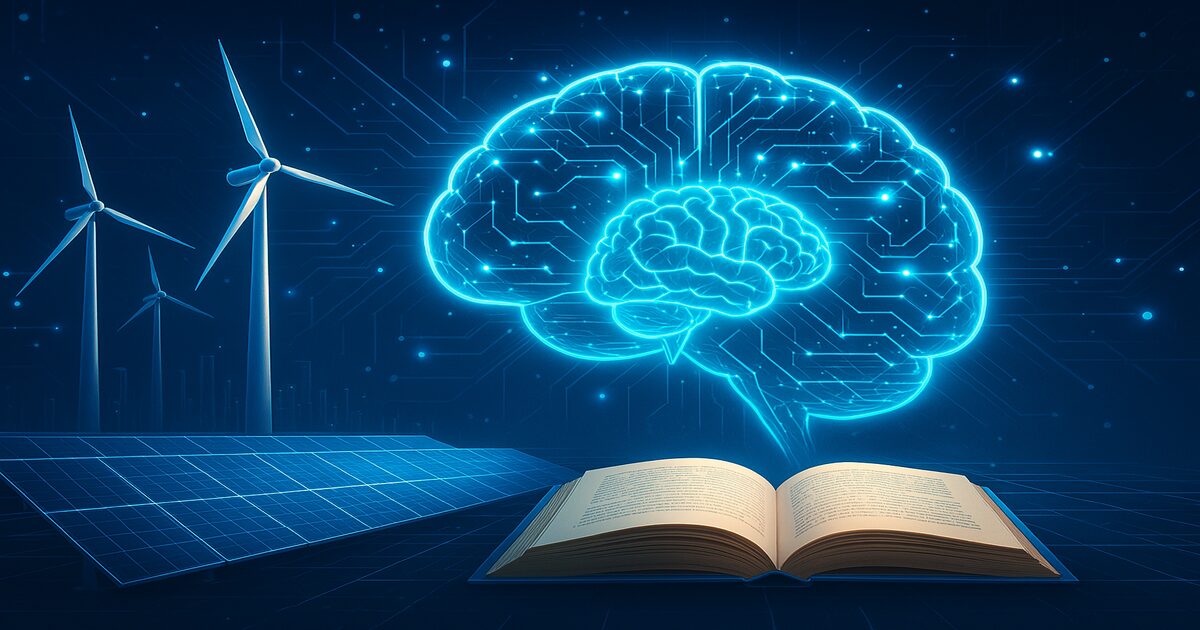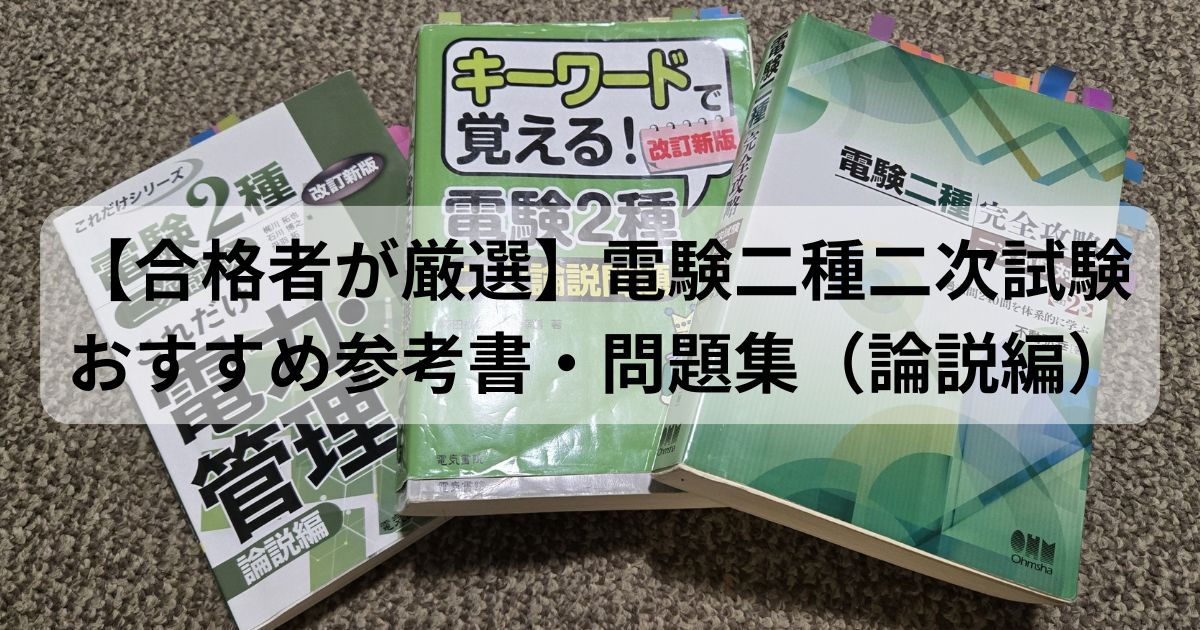「論説問題が覚えきれない…」
「参考書を読んでもすぐ忘れる…」
と悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
私自身、暗記が得意ではなく、特別に記憶力が良いわけでもありませんでした。
しかし、ただ“読むだけ”の勉強をやめて、ある暗記の工夫を取り入れたことで、『キーワードで覚える!』の内容を8割以上インプットでき、本番でも落ち着いて解答できました。
この記事では、私が実際に取り組んだ中で「これは効果があった」と実感できた、論説問題を効率よく覚える8つの暗記法を具体的に紹介します。
電験二種の論説対策で「効率的な覚え方」を探している方にとって、きっと役立つ内容です。
無駄な努力を減らし、暗記の質とスピードを同時に上げたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
🧱 電験二種二次試験の論説問題の壁は「記述できる暗記力」
電験二種の二次試験、特に論説問題において最大のハードルは、膨大な知識量を「記述できるレベル」で身につけることです。
記述式試験では、単に内容を理解しているだけでは通用しません。
自分の言葉で文章として書けるかどうかが問われるため、暗記の質と量の両方が重要になります。
✅ マークシート式との決定的な違い
選択肢形式の試験であれば、うろ覚えの知識でも「なんとなくこれかな?」という感覚で正解を導ける場合があります。
しかし記述式では、そうはいきません。
断片的な知識や理解レベルでは歯が立たず、正確な用語・表現を再現できるほど記憶に定着させておく必要があります。
私自身も、覚えたことをなかなか思い出せず、苦労しました。
このように同じ論説問題でもマークシート方式と記述式では暗記にかかる時間がまったく違います。
記述式は特に、しっかり内容を理解し、自分の言葉で再現できるようにしておく必要があるため、正直かなり根気がいります。
何度も繰り返さないと定着せず、心が折れそうになることもありました(笑)
🧠 合格者が実践した効率的な暗記方法
ここでは私が行った学習法の中で特に効果があった暗記法を厳選して紹介します。
その暗記法とは以下の8つです。
- 理解して暗記する
- 自分の言葉に言い換える
- キーワード中心に覚える
- アウトプットと間隔を空けた復習をする
- 同じ内容の問題はまとめて覚える
- 覚える箇所を絞る
- 共通している特徴に注目する
- 真逆の現象は片方だけ覚える
💡 理解を伴った暗記をしよう
電験二種の二次試験に出題される論説問題は、とにかく覚える量が多く、すべてを丸暗記するのは現実的ではありません。
だからこそ大切なのが、
理解して覚えること
理由や仕組みをセットで覚えることで、記憶の定着が格段に良くなります。
例:「地中配電系統のメリット・デメリット」を覚えるとき
地中配電系統の「配電線が地中にあるという特徴」をしっかり理解しておけば、メリット・デメリットも自然と頭に入りやすくなります。
✔ メリット
- 配電線が地中にあるため、雷や風雨・雪などの自然災害の影響を受けにくい
→ 信頼性が高い - 配電線が地中にあるため、車両や飛来物との接触もほぼない
→ 事故のリスクが低い - 電柱が不要なので、道路や歩道を有効活用できる
✔ デメリット
- 地中に埋設する工事が必要なので、建設費が高い
(工事のイメージを思い浮かべると納得しやすいですね) - 地中にあるため、事故が起きた際の発見や復旧に時間がかかる
- 地中にあるため、新たな配線の新設・増設がすぐにできない
→ 柔軟な対応が難しい
このように、単なる文章の丸暗記ではなく「なぜそうなるのか?」をセットで理解しておくと、関連付けて覚えることができ、試験本番でも思い出しやすくなります。
丸暗記に頼るのではなく、意味をしっかり理解しながら学習することを心がけましょう!
✏️ 自分の言葉で覚えやすく言い換えよう
論説問題を勉強していると、「キーワードで覚える!」のような参考書には、少し堅苦しくて難しい表現がよく出てきますよね。
もちろん、正確な用語を使うのは大事ですが、そのままだと覚えにくい…という場合は、自分なりにわかりやすく言い換えるのもアリです。
大事なのは「人に説明するなら、どう伝えるか?」を意識すること。
「要するにこういうことでしょ」と自分が腑に落ちる言葉で覚えておくと、本番でも思い出しやすくなります。
具体例:「微風振動」について
参考書の記述(一部抜粋):
比較的軽い電線が、電線と直角方向に毎秒数m程度の微風を一様に受けると、電線の背後に空気の渦(カルマン渦)が生じ、これにより、電線に生じる交番上下力の周波数が電線の固有振動数の一つと一致すると、電線が定常的に上下に振動を起こす。この振動が長年月継続すると電線が疲労劣化し、クランプ取り付け部の電線支持点付近で断線することがある。
…交番上下力??正直、読むだけで疲れますよね(笑)
✅ これを自分の言葉で言い換えると?
電線に微風が当たると、電線の後ろに空気の渦(カルマン渦)ができて、電線が上下に揺れ続ける。この振動が長く続くと、電線が劣化して断線することがある。
これくらいシンプルに言い換えても、内容はきちんと伝わりますよね!
論説対策では、「理解していることを自分の言葉で説明できるか」が大事な視点になります。
言葉づかいよりも、「伝える力」や「理解の深さ」が伝わるかを意識して勉強してみてくださいね!
🗝️ キーワードを中心に覚えるのが効率的!
参考書『キーワードで覚える!』の名前の通りですが、論説問題を勉強するときは**「キーワードを押さえること」**がとても効果的です。
論説の模範解答は、文章が長くてそのまま丸暗記するのはかなり大変…。
そこでおすすめなのが、
「キーワード+自分の言葉」で覚える方法
- まずは重要なキーワードだけをピックアップして覚える
- 覚えたキーワードを自分なりの言葉でつなげて文章にする
- 意味を理解していれば、自然と文章にできる
たとえば、こんな感じ!
微風振動について、「電線」「カルマン渦」「上下振動」「疲労劣化」「断線」などのキーワードを覚えておけば、
あとは自分の言葉でこんなふうに表現できます。
微風が電線に当たると、電線の後ろにカルマン渦ができて上下に揺れ続ける。この振動が長く続くと、電線が疲労劣化して断線することがある。
難しい用語や長文を丸暗記するよりも、はるかに覚えやすいですよね。
過去問の類題が少ない論説対策では、「完璧な文章を再現する」よりも、「理解して、伝えられる」ことの方が大切です。
キーワードを軸に、自分なりの言葉で表現できるようにしておくと、試験本番でも焦らずに対応できますよ!
🧠 アウトプットと「間隔を空けた復習」を重視しよう
論説問題は計算問題と違って、暗記が中心になるため、どうしても時間が経つと忘れてしまいやすいです。
だからこそ、論説対策では特に「復習の質」と「タイミング」が大事!
✅ 復習のタイミングは“忘れかけ”がベスト!
記憶には「エビングハウスの忘却曲線」という有名な理論があります。
これは、人は覚えたことをどんどん忘れていくという実験データに基づいたもの。
この理論を活かすには、以下のような方法がおすすめです👇
- 復習の間隔は、定着度に合わせて少しずつ広げる
- 「ちょうど忘れそうな頃」に思い出すのが最も効果的
- 最初は翌日、その次は1週間後、1か月後…というように間隔を広げて復習
💡 覚えるより“思い出す”ことが大切
覚えた内容を「思い出す」こと、これが記憶定着のカギです。
この“思い出す作業”はアクティブリコールと呼ばれていて、科学的にも非常に効果的とされています。
脳をしっかり使うため、インプットよりもアウトプットのほうが記憶に残りやすいんです。
🧠 アクティブリコールの活用法(私の体験)
私は机に向かっての復習だけでは時間が足りなかったので、日常のスキマ時間を活用してアウトプットしていました。
こんな感じでやってました👇
- 家事をしながら
- お風呂に入りながら
- ドライヤー中
- 職場での移動中(※安全には注意!)
やり方は簡単で、
- 家事やお風呂に入る前に問題文を読んでおく
- 問題文を頭に入れた状態で、上記作業中に頭の中で解答を再現する練習をする
これだけで、机に向かわなくても論説問題の復習ができます。
🔁 実際に行った「復習の間隔」
私はこんな感じで復習の間隔を設定していました👇
- 1回目:覚えた翌日
- 2回目:1週間後
- 3回目:1か月後
- 4回目:2か月後
最初はすぐ忘れてしまいましたが、何度も繰り返すことで、解説を見ればすぐに思い出せるレベルに!
最終的には、文章まるごと覚えてしまうほど定着しました(笑)
✅ 記憶力より「工夫」が大事!
私は特別に記憶力が良いわけではありません。
それでも、工夫して復習を重ねることで、しっかり記憶を定着させることができました。
暗記に苦手意識がある方こそ、「間隔を空けた復習」と「アウトプット」を意識してみてください。
地道ですが、確実に成果が出る方法です!
📚 同じような問題はまとめて覚えるのがコツ!
論説問題をたくさん解いていると、「これ、前に見た問題と内容がほとんど同じじゃない?」というような似た内容の問題に何度も出会うと思います。
でも、模範解答をよく見ると...
・使われている言葉が微妙に違ったり
・違う角度から説明されていたり
と、**一問ずつ丸暗記するのはキツイ!**ということも。
✅ 効率よく覚えるためのポイント
- 似たテーマの問題は“まとめて”覚える → 内容がほぼ同じなら、共通する部分を自分なりに整理して覚える
- 丸暗記より“意味を理解する”ことが大事 → 表現が違っても、意味が分かっていれば自分の言葉で書ける
- エクセルやノートにまとめる → 同じような問題をセットにして、共通点や違いを一緒に記録すると記憶に残りやすい
🎯 覚える箇所は“絞る”のが効率的!
最初に「理解の伴った暗記が覚えやすい」とお伝えしましたが、すべてを完璧に覚えようとする必要はありません。
特に、意味がよくわからない部分やどうしても覚えづらい内容に関しては、無理に詰め込まなくても大丈夫です。
✅ 効率的な覚え方のポイント
- 参考書の内容を全部覚えようとしなくてOK!
→ 参考書には「特徴・長所・短所」がたくさん載っていますが、実際の試験で問われるのは2~3個程度。 - 優先すべきは“理解しやすくて覚えやすいもの”
→ 試験で使いやすく、思い出しやすい内容を中心に暗記するのがベスト。 - 覚えにくいもの・意味不明なものは無理に詰め込まない
→ 私も実際に、意味がピンとこない部分やあまり重要でなさそうな部分は、思い切ってスルーしていました。
私は論説問題の解答を丸暗記するのではなく、重要な部分だけをピックアップして覚えるようにしていました。実際には、参考書の覚えるべきポイントにアンダーラインを引いたりして、メリハリをつけて暗記していました。
例えば、太陽光発電の特徴に関しては、全部で11個もありましたが、正直すべてを覚えるのは大変です。
そこで私は、本文でも太字になっている重要そうな6つの特徴だけを暗記しました。
こうすることで、覚える量を無理なく減らしつつ、試験に出やすいポイントに集中できたので、効率よく勉強を進めることができました。
「全部覚えなきゃ!」と頑張りすぎると、かえって頭がパンクしてしまいます。
優先順位をつけて、“覚えるべきポイント”を絞ることが、合格への近道です!
🔎 共通している特徴に注目して覚える
論説問題では、それぞれの発電方式や設備に特徴がありますが、中には**「共通している特徴」**もたくさんあります。
たとえば、太陽光発電や風力発電といった自然エネルギーを使う発電方式には、次のような共通点があります。
✅自然エネルギー発電の共通する特徴
- クリーンな発電方式(CO₂を排出しない)
- 発電コストが高め
- 枯渇しないエネルギーを利用
- エネルギー密度が小さい
- エネルギー変換効率が低い
- 発電が天候や自然条件に左右されやすい
これらは、太陽光発電・風力発電などに共通する特徴なので、まずはこの“共通項”をまとめて覚えてしまいましょう!
そして、あとは各発電方式にしかない固有の特徴だけを覚えればOKです。
このように、似ているもの同士の“共通点”を先に覚えてしまうと、暗記がぐっとラクになります。
効率的に覚えたい方にはとてもおすすめの方法ですよ!
🔄 「真逆」の現象は片方だけ覚えればOK!
理系の勉強では、「ある現象の逆パターン」もよく出てきますよね。
でも、実は片方の流れをしっかり理解して覚えておけば、逆はそのまま“反転”するだけなんです。
✅ 例:BWR(沸騰水型原子炉)の出力制御
BWRでは、中性子吸収材が充填された制御棒を使って出力をコントロールします。
制御棒を原子炉内に挿入する場合
- 制御棒に吸収される中性子が増える
- 核分裂反応が減る
- 原子炉の出力が下がる
制御棒を原子炉内から引き抜く場合
- 制御棒に吸収される中性子が減る
- 核分裂反応が増える
- 原子炉の出力が上がる
このように、挿入と引き抜きは真逆の動きです。
つまり、どちらか一方の流れを覚えてしまえば、もう一方は逆として覚えればOK!
暗記が大変な論説問題では、「逆の現象」はおいしい暗記ポイント。
無理に両方覚えようとせず、理解+逆パターンで効率的に攻略していきましょう!
✅まとめ:効率的に暗記して論説問題で得点アップ
今回は、私が実際に実践した論説問題の効率的な暗記法を8つ紹介しました。
内容的には、すでに「当たり前」と感じる部分もあるかもしれませんが、実際にアウトプットを取り入れたり、復習のタイミングを工夫することで、記憶の定着が大きく変わります。
さらに、暗記量を減らす工夫をすることで、効率よく学習できるはずです。
論説問題で得点できるように、ぜひこれらの方法を試してみてください!
効率的な暗記を実践して、少しでも楽に試験勉強を進められるよう応援しています!
下記の記事では論説対策でおすすめの参考書・問題集を紹介しています。
こちらもぜひ参考にしてみてください!