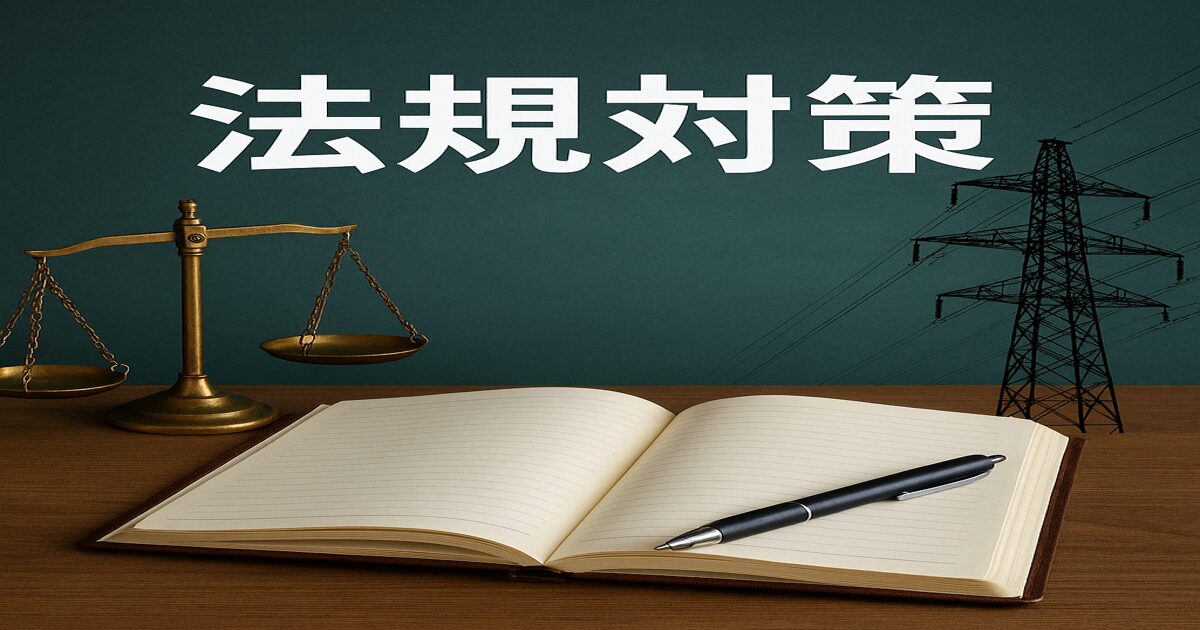「法規って暗記が多くて大変」
「過去問を解いても、点数が安定しない…」
そう感じたことはありませんか?
電験三種の法規科目は、法令・制度の暗記だけでなく、計算問題も出題されるという、少しクセのある科目です。
見落としがちな細かい知識や、過去問とは少し違った切り口の出題もあり、実は“最後の落とし穴”になりやすい科目でもあります。
私は独学で電験三種に一発合格しましたが、法規科目は88点と高得点を取ることができました。
この記事では、私自身の学習経験をもとに、
- 法規科目の出題傾向と頻出テーマ
- 暗記と計算の効率的な学習バランス
- 法規を「苦手科目」から「得点源」に変えるコツ
をわかりやすく解説していきます。
法規で安定して得点を取れるようになりたい方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。
🔍 法規科目の特徴を押さえよう!
法規科目は、電験三種の中でも少し異色の存在かもしれません。
というのも、他の3科目(理論・電力・機械)が技術的な内容を中心に出題されるのに対し、法規は「ルールや基準」を問う科目だからです。
試験では、電気事業法・電気設備技術基準・電気用品安全法といった法律の知識に加えて、実務に関わる計算問題も出題されます。
つまり、**知識問題と計算問題の“ハイブリッド型”**といえる構成です。
内容が暗記寄りなので、対策のやり方を間違えると「覚えたはずなのに選択肢で迷って落とす…」なんてことにもなりがちです。
でも逆に言えば、しっかり対策すれば安定して得点できるのが法規。
理論や機械が苦手でも、法規でカバーすることもできます!
ここでは法規科目の特徴について解説していきます。
- 法規科目の位置づけと重要性
- 他科目との関連性
🎯 法規科目の位置づけと重要性
法規は、安全・法律・ルールを正しく理解しているかどうかを問う科目です。
電気設備に関する技術基準や法令は、現場で電気を扱う人にとって最も重要な知識のひとつ。
つまり、「現場で電気を扱う資格者としての責任」を問われているともいえます。
また、過去問の類似問題が出やすく、出題傾向が安定しているのもポイント。
暗記中心ではありますが、短期間でも集中的に取り組むことで得点源にしやすい科目でもあります。
🔗 他科目との関連性(理論・電力・機械とのつながり)
法規は単独の知識だけでなく、理論・電力・機械の内容と重なる部分もあります。
例えば:
- 電力と重なる内容
- 力率改善、需要率・負荷率・不等率などの計算問題
- 水力・火力・原子力発電に関する特徴や所内率など
- 理論と重なる内容
- 電圧降下、配線設計、電線の太さに関する内容
- 機械と重なる内容
- 電動機の始動方式や保護装置の選定
- 変圧器の全日効率の計算
このように、他科目の理解が法規でもそのまま活かせる場面が多く、トータルでの得点力アップにもつながります。
📊 法規科目の出題傾向と難易度を分析!
法規は「なんとなく暗記科目で難しそう…」と思われがちですが、出題傾向は安定しています。
しっかり勉強すれば得点源にもできるので、苦手意識を持たずに取り組んでほしいところです!
ここでは法規科目の出題範囲と難易度について解説します。
- 出題範囲
- 知識問題と計算問題のバランス
- 難易度の特徴
📌 出題範囲は広いが、頻出分野に絞って対策すれば戦える!
法規は法律や基準が絡むため、一見すると範囲が膨大に見えます。
でも実際には、毎年のように問われる「頻出テーマ」が決まっているので、そこをしっかり押さえるだけでも十分戦えます。
特に狙いたいのはこのあたり👇
- 電気設備技術基準とその解釈(技術基準)
→ 出題率高め!設置場所や接地工事の種類などを押さえる - 電気事業法、電気用品安全法
→ 条文の細かい部分より、全体像・重要な条文に集中 - 保安管理、主任技術者の職務
→ 実務に関わるポイントがよく出題される - 需要率・負荷率・所内率などの計算問題
→ 他科目ともかぶるので、まとめて対策できる
すべてを覚えようとせず、「よく出るところに絞って繰り返し覚える」のが効率的です!
⚖️ 知識問題が中心だが、計算問題も出題される
法規=暗記だけ、と思っていると意外と苦戦します。
知識問題:計算問題=6:4で出題されるので、計算問題を落とさないかどうかが合否の分かれ目になります。
出やすい計算問題のパターンはこんな感じ👇
- 力率改善の計算(進相コンデンサ投入)
- 発電所の出力や所内率に関する計算
- 電線のたるみの問題
- 負荷率・不等率・需要率の計算
- 変圧器の効率計算
特に「電力」との被りが多いので、電力と法規の計算はセットで覚えるのがおすすめです。
🧱 法規は電験三種の中でも難関科目の一つ
法規は4科目の中でも「難しい」と感じる受験生が多く、年度によっては合格率がグッと下がることもあります。
その理由の一つが、覚えるべきことが多くて、しかも覚えにくいという点です。
特に難しいと感じるポイントは以下のような部分👇
- 条文の内容を暗記する必要がある
→ 技術的な理解ではなく、ほぼ丸暗記になりがち - 似たような表現や数値が多くて混乱しやすい
→ 少し表現が違うだけで意味が変わるので注意が必要 - 毎年どこかしら初見の条文が出ることも
→ 「見たことない!」と焦らないメンタルも必要 - 技術的な裏付けがないためイメージが湧きにくい
→ 電力や機械と違って“考えて理解する”が効きにくい - 時事問題が出ることがある
→ 電気事業法や再生可能エネルギー関連など、直近の法改正やトピックが問われることがあり、過去問だけでは対応できないケースも
例えば電力や機械では、「モータはこういう原理だからこうなる」といった理解で覚えられる場面が多いですが、
法規では「何ボルト以上で○○が必要」「○○m以内に設置」など、決まった数字や条文をそのまま覚える必要があるため、手こずりやすいんですよね。
とはいえ、頻出の条文や数字に絞って覚えていけば、確実に点は取れます。
広く浅くより、「よく出るところを深く」が合格のカギです!
🎯 対策のポイント
ここでは、私自身の経験をもとに、法規の学習で意識すべきポイントを4つにまとめました。
- 法規は最後に学習する
- 知識問題は正確に覚える
- 計算問題を得点源にする
- 計算問題は機械や法規と合わせて理解する
🗓️ 法規は最後に学習するのが効率的!
法規は暗記中心の科目なので、早い段階から始めても試験本番までに内容を忘れてしまうことが多いです。
実際、私も本格的に法規の暗記を始めたのは試験の3ヶ月前でしたが、それでも十分に間に合いました。
さらに法規では、理論・電力・機械といった他の3科目で扱った専門用語や知識がそのまま出てくることもあります。
そのため、他科目をある程度理解したうえで取り組む方がスムーズに進められます。
✅法規対策を後回しにする理由
- 暗記中心なので、早く始めると忘れやすい
- 他の3科目の知識がベースになることが多い
- 最後に集中的に覚えるほうが記憶に残りやすい
特に独学の方は、いきなり法規から取りかかると「この用語初めて聞いた…」とつまずきやすいです。
まずは理論・電力・機械を固めてから、法規は“仕上げ”として学ぶイメージで進めると効率的ですよ!
🧠 知識問題は正確に覚えて得点源に!
法規の知識問題では、条文の穴埋め問題が多く出題されます。
一見すると、選択肢のどれもが正しそうな日本語なので、しっかり覚えていないと迷いやすいんですよね。
条文は「なんとなくこういう意味かな?」と推測で解けるものではないので、正確に覚えることが必須です。
ただし、条文を最初から最後まで丸暗記するのはかなり大変…。
そこでおすすめなのが、頻出の箇所に絞って効率よく覚えることです。
実際に私が活用して効果があったツールは以下の2つです👇
- 🔖 電験合格の暗記プリント
→ よく出る条文の「穴埋め」形式になっていて、試験に出やすいポイントを重点的に覚えられる - 📱 法規アプリ
→ 広範囲をカバーしていて、私が受験した時にアプリと“まったく同じ問題”が出題されたこともありました!
暗記プリントは頻出分野の法令や重要ポイントが穴埋め形式になっていて、空欄のままのプリントと空欄に答えが書いてあるプリントのセットになっています。
プリントはYouTubeチャンネル「電験合格」演習編(法規)の概要欄にダウンロード先が貼られています👇
法規アプリも穴埋め形式の問題が中心です。
下記のリンクからインストールできます👇
また、法規では穴埋め問題だけでなく、正しい文章の選択肢を選ぶ形式の問題も出題されます。
このタイプの問題では、記憶があいまいだと「なんとなくそれっぽい選択肢」に引っかかりがちなので注意。
暗記とあわせて、以下のような対策もおすすめです👇
- 過去問を使って、実際の出題形式に慣れておく
- 覚えた内容を“使える知識”にするためにアウトプット中心の勉強を意識する
- 似た数値や表現は比較しながら覚えて混乱を防ぐ
しっかり暗記していれば、法規の知識問題は確実な得点源にできます。
焦らずコツコツ積み上げていきましょう!
🔢 計算問題を得点源にすれば合格がグッと近づく!
法規の試験は100点満点ですが、そのうち計算問題が約40点分を占めています。
この計算問題で30点以上取ることができれば、残りの知識問題では半分正解するだけで合格点に届きます。
つまり、計算問題を得点源にできれば、合格ラインが一気に現実的になるんです!
また、法規科目の計算問題は、たまに難しい問題が出ることもありますが、基本的にはある程度パターン化されているのが特徴です。
そのため、よく出る問題パターンや公式を押さえておけば、十分に得点源になります。
ちなみに私は法規の計算問題は満点でした!計算パターンをしっかりマスターすれば満点も充分可能です!
公式はただ暗記するのではなく、「なぜこの式になるのか?」という意味を理解した上で、必要最低限の公式を覚えることが大切です。
✅ 対策のポイント
- 過去問や問題集で繰り返し練習して慣れる
- よく出る計算パターンを押さえる
- 公式は意味を理解して覚える
- 導出・変形できるように練習する
知識問題に比べて、計算問題は「覚えれば解ける」というよりも、しっかり理解してパターンに慣れれば安定して得点できるのが強み。
過去問や演習問題を繰り返して、確実に取れる問題をモノにしていきましょう!
🧮 電力や機械の計算問題は法規にも登場!
機械科目や電力科目で学ぶ計算問題の中には、法規科目でも同じ内容が出題されるものがあります。
そのため、法規と合わせて勉強しておくと効率的に理解が深まり、どちらの科目でも得点源にしやすくなります。
特に以下のようなテーマは、どちらにもよく出てくるので要チェックです。
🏭 電力と法規の両方で出題される代表的な計算問題
- 進相コンデンサ投入による力率改善の計算
- 発電所に関する出力・効率などの計算
- 不等率・需要率・負荷率の関係や計算
- 電線のたるみに関する計算
⚙️ 機械と法規の両方で出題される代表的な計算問題
- 変圧器の損失・効率・全日効率の計算
これらの問題は公式を覚えるだけでなく、「なぜそうなるのか?」を理解しながら取り組むことがポイントです。
機械や電力で計算の基本を学びつつ、法規で実務にどう活かされているかまで意識して学習すると、知識がより定着しやすくなりますよ。
✅ まとめ:法規科目を攻略して電験三種合格をグッと近づけよう!
今回は、電験三種の「法規」科目の特徴と対策のポイントについてお伝えしました。
✅ 本記事のまとめポイント
- 法規科目は暗記が中心なので最後に学習するのが高効率
- 知識問題は正確に覚えて得点源にしよう
- 計算問題はパターン化されているので、十分な得点源
- 計算問題は電力、機械と合わせて理解しよう
法規科目は、理論・機械・電力のような技術的な面白さが少なく、勉強していてもモチベーションが上がりにくい科目かもしれません。
また、条文の暗記や範囲の広さなど、対策が難しいと感じることもあると思います。
それでも、今回ご紹介したようなポイントを押さえて計画的に取り組めば、しっかり合格点を狙うことができます。
もし独学に不安がある方は、通信講座を活用するのも一つの手です。
重要ポイントが整理されていたり、効率よく学べる教材がそろっているので、学習のペースをつかみやすくなりますよ。