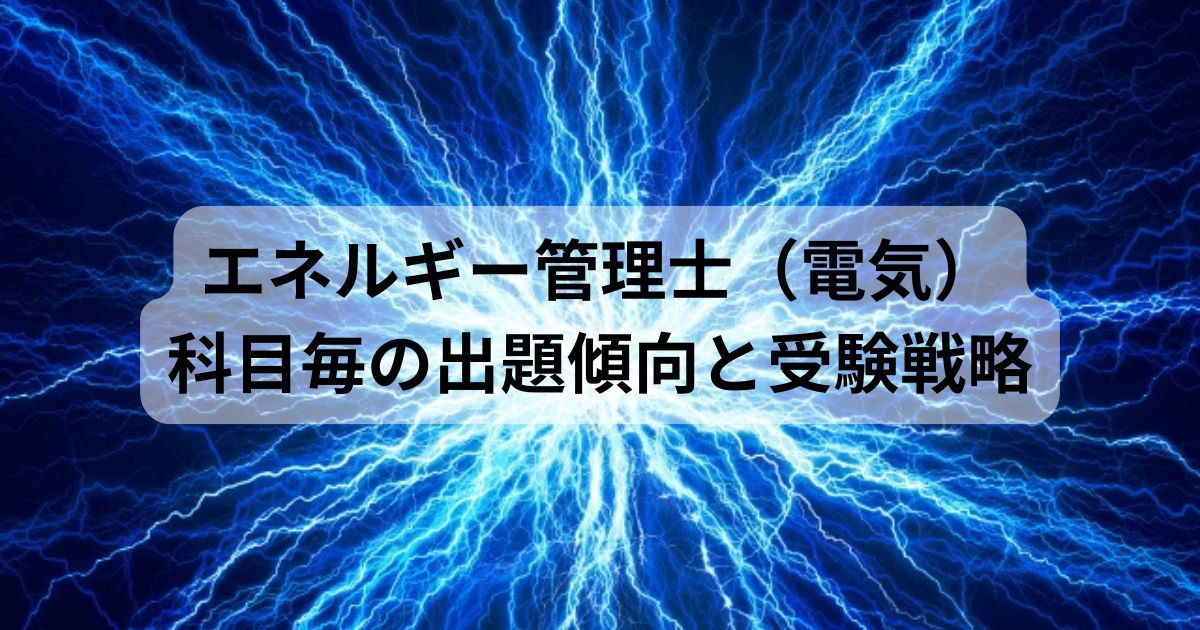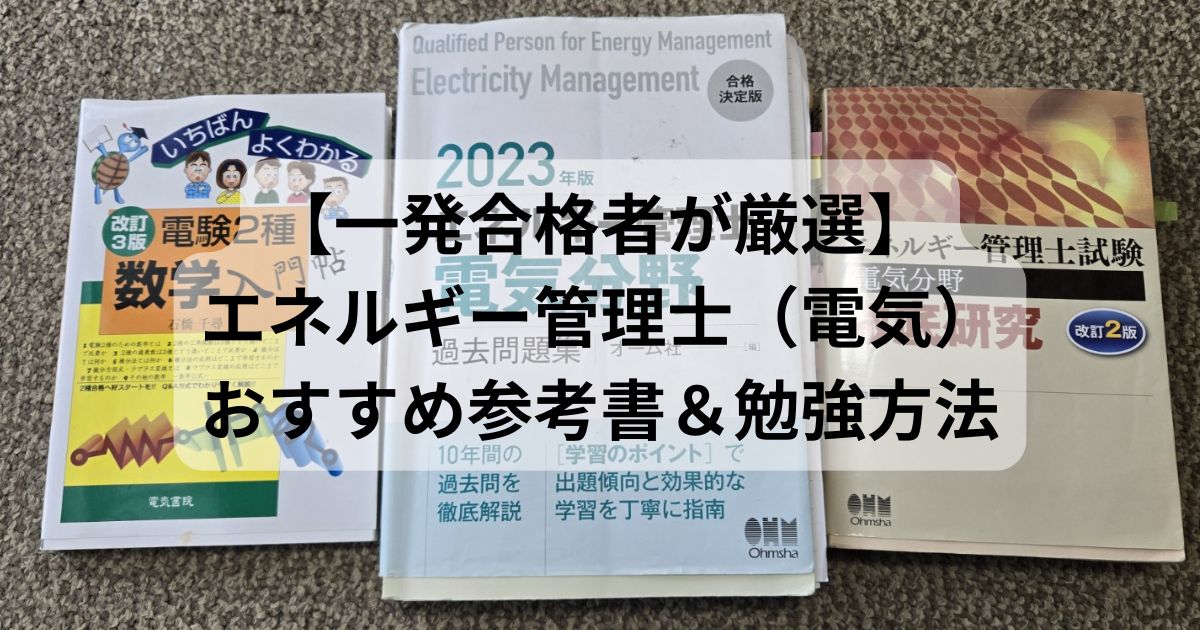エネルギー管理士(電気)は、電験三種取得者が多く受験することもあり、「難易度が高く、独学では厳しい」という印象を持たれがちです。
特に悩みやすいのが、試験中の時間配分や、どの問題から解くべきかという“受験戦略”の部分。
問題の難易度や出題形式が科目ごとに異なるため、適切な順番や時間配分を意識しないと、最後までたどり着けずに終わってしまうことも…。
私自身、電験三種を取得後にエネ管(電気)に挑戦し、初受験・一発合格を果たしました。
この記事では、その経験をもとに、各課目の出題傾向と実践して効果があった解答順・時間配分・戦略の立て方を詳しく解説します。
「どの問題から手を付けるべき?」
「時間が足りなくなるのが不安」
「時間配分の目安は?」
そんな疑問や不安を解消し、本番で最大限に実力を発揮するためのヒントが詰まっています。
初学者・独学の方でも、効率的に合格を目指せるような内容にしていますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
🎯 エネ管(電気) 科目別の傾向と合格者が実践した戦略
⚖️ 課目Ⅰ:エネルギー総合管理及び法規
📚 出題内容と特徴
- 試験時間:80分
- 問題数:全3問(問題1,2が各50点、問題3が100点の合計200点)
- 出題傾向:
- 問題1:条文の穴埋めや、工場でのエネルギー使用量に関する実務的な問題
- 問題2:単位換算やエネルギー情勢・政策
- 問題3:熱や電気に関する基本的な計算問題が中心
📌 私の戦略と考え方
この科目では、得点源かつ配点が最も高い問題3からスタートするのが私にとっての鉄則でした。
- 解答順:問題3 → 問題1 → 問題2
- その理由:
- 問題3は配点が高く、計算問題が簡単なので得点源。
- 問題1も、出題パターンが安定していて、過去問で対策しやすく確実に点を取れるポイント。
- 問題2は、単位換算は取りやすいものの、「エネルギー情勢・政策」については、参考書や過去問にも出てこない知識勝負の運ゲー要素があり、後回しに。
- 時間配分の目安:
- 問題3:30分
- 問題1:20分
- 問題2:20分
- 見直し:10分
💭 本試験の手応えと評価
- 問題3は85点と高得点
- 問題1は私が受験した令和5年度に法改正があり、改正された部分で失点
- 問題2は単位換算は得点できたものの、知識問題で失点が目立つ
- 総合得点は138/200点(正答率:69%)と4科目の中で最も低い結果に
⚡ 課目Ⅱ:電気の基礎
📚 出題内容と特徴
- 試験時間:80分
- 問題数:全3問(各50点、合計150点)
- 出題傾向:
- 問題4:直流・交流回路、ベクトルなどの回路計算
- 問題5:自動制御や情報処理に関する計算・知識問題
- 問題6:電気計測に関する基礎知識・計算問題
📌 私の戦略と考え方
この科目では、問題4の回路計算をどれだけ早く正確にこなせるかがカギでした。
- 解答順:問題4 → 問題6 → 問題5(もしくは問題6→問題4→問題5)
- その理由:
- 問題4は電験三種の理論の知識が活かせるので得点源。ただし、計算が多く、つまずくと手が止まってしまう危険も。自信がない人は問題6を先に解くのも◎
- 問題6は暗記要素が多くスムーズに解けることが多かったので、気持ちよく得点できました。
- 問題5の自動制御は計算にやや時間がかかるが、過去問でパターンを押さえれば対応可能。情報分野は参考書や過去問にも載っていない未知の問題が出るので、運ゲー要素あり。
- 時間配分の目安:
- 問題4:30分
- 問題6:15分
- 問題5:25分
- 見直し:10分
💭 本試験の手応えと評価
- 問題1の回路計算は途中で手が止まり焦ったがなんとか持ち直した
- 問題2、問題3の知識問題は実務で知っていた問題やカンで正解した問題もありしっかり得点
- 総合得点は124/150点(正答率:82.6%)
🏭 課目Ⅲ:電気設備及び機器
📚 出題内容と特徴
- 試験時間:110分
- 問題数:4問(各50点、合計200点)
- 出題傾向:
- 問題7・8:配電線・配電設備(知識+計算問題)
- 問題9・10:モーター・変圧器(四機)やパワエレ関連(知識+計算問題)
📌 私の戦略と考え方
この科目は**「電験三種の電力+機械」で解ける内容**が中心で、全体的に取り組みやすく感じました。
- 解答順:特にこだわりなし(自信がある問題から順に)
- ポイント:
- 全体的に知識ベース+計算という構成。
- 計算問題は時間がかかるため、1問に20〜25分を目安にタイムマネジメントが重要。
- 難問は少ない印象でしたが、思考力を要する計算で手が止まりやすいので、集中力の維持が合否の分かれ目に。
💭 本試験の手応えと評価
- 計算問題は途中で合っているか自信がなかったが、しっかり得点できていた
- 知識問題はほぼ完答
- 総合得点は176/200点(正答率:88%)と4科目の中で最高得点
💡 課目Ⅳ:電力応用
📚 出題内容と特徴
- 試験時間:110分
- 問題数:必須2問+選択2問(計4問)
- 配点:各50点、合計200点
- 私が選択した出題分野:
- 問題13:電気加熱(知識+計算問題)
- 問題15:照明(知識+計算問題)
- 問題11〜12:インバータや電動機、ポンプ・送風機などの必須問題(知識+計算問題)
📌 私の戦略と考え方
選択問題の2問を得点源にできるかがカギになります。私は**「電気加熱」と「照明」**を選びました。
- 解答順:選択問題 → 必須問題
- その理由:
- 選択問題は過去問と似た傾向が多く、短時間で高得点が狙える。
- 必須問題は難易度が高く、特に電動機の問題は毎年難問がある為、選択問題を短時間で終わらせ、必須問題に時間を割く。
- ポンプや送風機の効率計算、インバータ関連の知識問題などは比較的安定して得点できる分野なので先に解く。
- 時間配分の目安:
- 選択問題:各20分
- 必須問題:各30分
- 見直し:10分
💭 本試験の手応えと評価
- 選択問題の計算問題は完答し、知識問題は一部カンで正解したのもあり高得点
- 選択問題の照明で意外と時間がかかり、必須問題が最後まで解けずに悔しい
- 総合得点は161/200点(正答率:80.5%)と最難関科目で8割以上取れたのは満足
✍️ 最後に:私が大切にした「3つの軸」
エネルギー管理士(電気)の試験は、1科目ごとに出題形式や難易度の傾向が大きく異なります。
私自身、一発合格を目指す中で「解く順番」「時間配分」「得点戦略」の3つを常に意識して取り組みました。
私が合格まで大切にした3つの軸は、以下の通りです。
🔑 私が意識していた3つの軸
- 得点源を見極めて解く順番を決めること
→ 自分にとって確実に点が取れる問題を最初に解いてリズムを作る。 - 1問にかける時間の目安を持ち、迷ったら潔く次へ進む判断力
→ 手が止まると時間が足りない。タイムマネジメントは合否を分けるカギ。 - 「取れる問題で確実に点を取る」戦略を徹底すること
→ 難問に固執しない。8割主義で堅実に積み上げていく姿勢。
この3つを意識したことで、本番でも大きく崩れることなく、各科目を乗り切ることができました。
あなたもぜひ、自分なりの「得点戦略」と「時間配分」を持って、エネ管(電気)を攻略してください!
📝 あわせて読みたい!エネ管(電気) 受験対策のおすすめ記事
エネ管(電気)の受験を考えている方に向けて、他にも役立つ記事をまとめました👇
ぜひこちらもチェックして、合格に向けた準備を万全にしましょう!