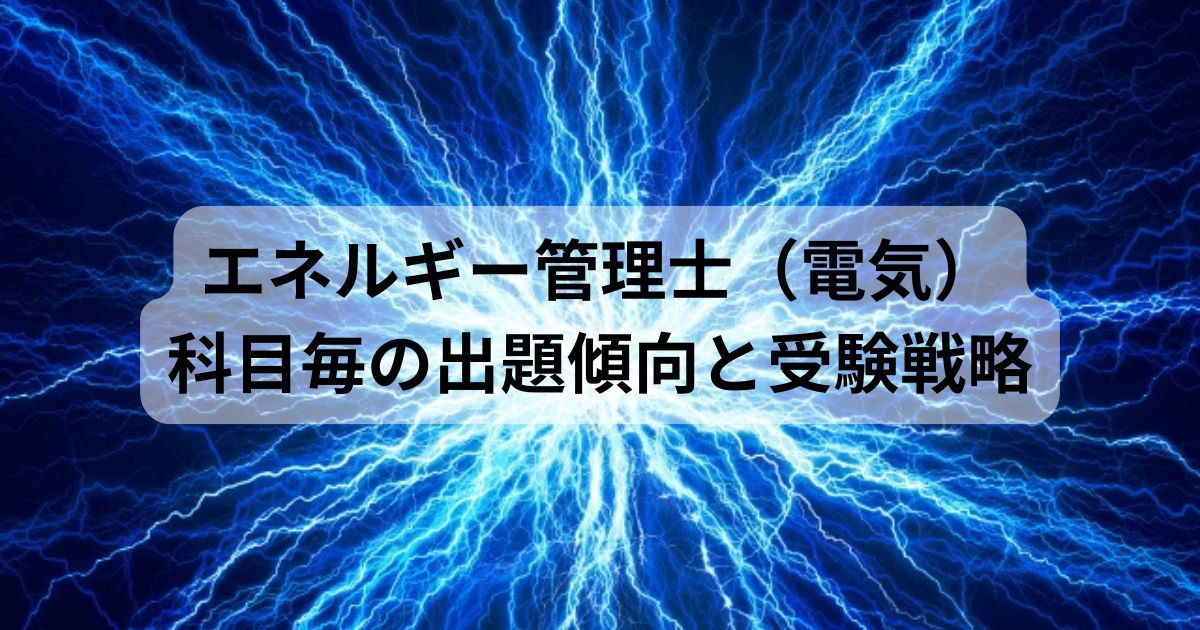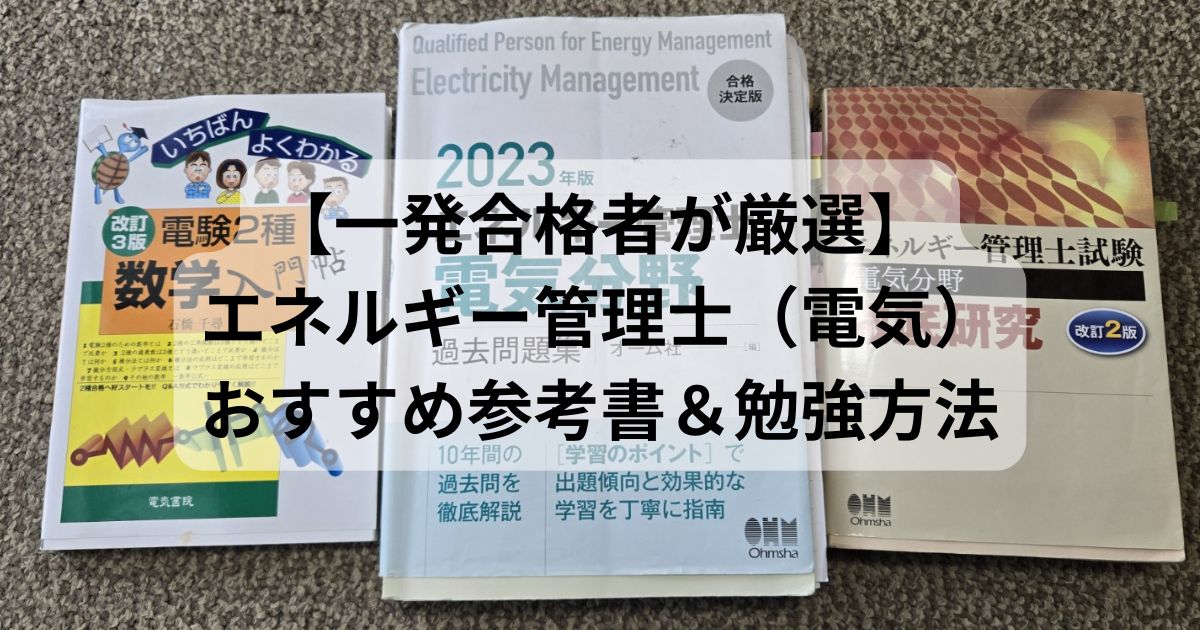私は令和5年度にエネルギー管理士試験(電気分野)を受験し、無事一発合格することができました!
この記事では、実際に受験したときの試験会場の雰囲気や、試験中に感じたこと、当日のリアルな様子をまとめています。
これからエネルギー管理士試験に挑戦しようと思っている方に、少しでも役立つ情報をお届けできればうれしいです。
目次
【合格者が語る】試験当日の科目別リアルレポート
試験当日のリアルな様子を、各科目ごとに振り返っていきます。
問題の傾向や、実際に感じた難易度、試験中の心境など、受験生目線で正直にまとめました。
これからエネルギー管理士(電気)試験に挑戦する方の参考になれば嬉しいです!
📅 時間割
| 時限 | 科目 |
|---|---|
| 第1時限目(9:00~10:20) | 課目Ⅰ:エネルギー総合管理及び法規 |
| 第2時限目(10:50~12:40) | 課目Ⅲ:電気設備及び機器 |
| 第3時限目(14:00~15:50) | 課目Ⅳ:電力応用 |
| 第4時限目(16:20~17:40) | 課目Ⅱ:電気の基礎 |
なお、試験問題と解答は下記のリンクから確認できます。
ECCJ 省エネルギーセンター / エネルギー管理士 / 過去の試験問題
第1時限目【課目Ⅰ:エネルギー総合管理及び法規】(9:00~10:20)
まずは課目Ⅰからスタート。
令和5年度の試験は、省エネ法の改正があったため、「どれくらい影響が出るのか?」と少し構えていました。
改正によって、工場のエネルギー量の計算方法が変わるという話もありましたが、事前の情報では「改正部分は知識問題のみで、計算問題には影響なし」とされていたので、直前にポイントだけ軽く押さえて臨みました。
試験本番、問題1の【条文】については、需要の「平準化」→「最適化」への変更はちゃんと頭に入れていたのでバッチリ解答できました!
ただ、エネルギーの定義に出てきた「非化石熱」や「非化石電気」については完全にノーマーク…。ここは手が出せず。
【工場のエネルギー計算】では、「なるほど、そうきたか!」という印象。
これまでは、工場のエネルギー使用量を自分で計算してから、必要なエネルギー管理者や管理員の人数を求めるパターンが定番でしたが、今回は計算後のエネルギー使用量が提示されていて、その数字から答える形式に変わっていました。これも、省エネ法改正の影響ですね。
問題1の自己採点は28/50点。
問題2の単位換算はスムーズに解けたものの、その他の問題で失点が響き、自己採点は25/50点。
問題3は【計算問題】で、ここは毎年似たようなパターンの出題が続いており、しっかり対策していたので得点源に。自己採点は85/100点と好調でした。
時間にも余裕があったので「課目Ⅰは余裕かも!」と油断していたのですが、結果的には4科目の中で一番低い得点に…。
最終的なスコアは138/200点(69%)でした。
第2時限目【課目Ⅲ:電気設備及び機器】(10:50~12:40)
課目Ⅲは、過去問演習でも一番得点率が高かった自信のある科目でした。
知識問題については、特に引っかかることもなくスムーズにクリア。
ただ、計算問題については、解きながら「これ合ってるかな…?」と若干の不安を感じながら進めていました。
それでも、「合格点を下回ることはないだろう」という手応えはありましたね。
試験後に答え合わせをしてみると、不安だった計算問題はしっかり正解していて一安心。
細かい部分でいくつかミスはあったものの、知識問題はほぼパーフェクト。
自己採点の結果は【176/200点(88%)】と、4科目の中でダントツの高得点!
過去問の演習で取れていた点数そのままを本番でも出すことができ、かなりいい流れで前半戦を終えることができました。
第3時限目【課目Ⅳ:電力応用】(14:00~15:50)
昼休みを挟んで、いよいよ最難関の課目Ⅳに突入です。
まずは問題をざっと一通り確認。
そして問題12を見た瞬間、思わず笑っちゃいましたね(笑)。
課目Ⅳでよく出る、かなり高度な内容だけど「誘導に従えば何とか解ける」というタイプの問題。こういう問題は、誘導にちゃんと乗っかれば得点できる可能性は高いんですが、とにかく時間がかかる…。なので、ひとまず後回しにする作戦を取りました。
まず手を付けたのは、比較的点が取りやすい選択科目の【電気加熱】と【照明】。
特に照明の計算問題で、問題文の解釈によって答えが分かれそうな、ちょっと不親切な問題があり、だいぶ悩まされました…。イライラしながらも時間をかけて何とか対応。
結果的に、電気加熱と照明の計算問題は満点!知識問題も、カンが当たったところもありつつ、しっかり高得点を取れました。
続いて問題11へ。
ここは【誘導電動機の知識問題】と【走行台車のエネルギー計算】。
このエネルギー計算の問題、最初は全然理解できなかったんですが、過去問を何度も繰り返すうちにしっかり押さえられるようになり、本番では完答できました!
誘導電動機の知識問題で若干の失点はあったものの、自己採点は44/50点と上々の結果。
そして最後に、いよいよ問題12。
後半は送風機に関する単位法を使った計算問題でしたが、これも最初は全く分からなかった分野。しかし、パターンがほぼ決まっているので、過去問でしっかり対策して得点源にすることができました。
とはいえ、照明で予想以上に時間を取られてしまったため、問題12の前半の誘導に乗っかるタイプの問題が最後まで解き切れず…。ちょっと悔しさは残りましたが、自己採点の結果は【161/200点(80.5%)】!
最難関と言われる課目Ⅳでこの得点を取れたのは、素直に満足しています。
第4時限目【課目Ⅱ:電気の基礎】(16:20~17:40)
ラストは課目Ⅱ、電気の基礎です。
もうここまで来ると、疲労感もかなりありましたが、最後の力を振り絞って臨みました。
まず問題4の【回路計算】。
普段、過去問ではほぼ完答できていた分野だったんですが、今回は途中でわからないところに引っかかってしまい、かなり焦りました…。
それでも何とか立て直して解き切ることができ、自己採点は【45/50点】。
続く問題5の【自動制御】では、いくつかミスはあったものの、全体的にはそれなりにできました。
【情報処理】の問題は、ほぼカン頼みで解いた部分もありましたが、運良く正解してくれて、問題5の自己採点は【39/50点】。
そして問題6の【電気計測】。
ここでは、オシロスコープの高速フーリエ変換(FFT)や標準偏差の2σに関する問題などは実務での経験が役立ち、しっかり解答することができました!自己採点は【40/50点】。
最終的な総合得点は【124/150点(82.6%)】。
手応えとしては、「まあまあできたかな」と思える内容で、無事に最後まで走り切ることができました。
試験結果(自己採点)
令和5年度のエネルギー管理士(電気)試験について、公式解答と照らし合わせて自己採点した結果をまとめました。
自己採点(総合得点)
| 科目 | 得点 | 正答率 | 判定(合格基準) |
|---|---|---|---|
| 課目Ⅰ | 138/200点 | 69% | ◎ 合格(60%以上) |
| 課目Ⅱ | 124/150点 | 82.6% | ◎ 合格(60%以上) |
| 課目Ⅲ | 176/200点 | 88% | ◎ 合格(60%以上) |
| 課目Ⅳ | 161/200点 | 80.5% | ◎ 合格(60%以上) |
各課目の設問別 得点内訳
⚖️ 課目Ⅰ(エネルギー総合管理及び法規)
- 問題1(法令):28/50
- 問題2(エネルギー情勢):25/50
- 問題3(計算):85/100
⚡ 課目Ⅱ(電気の基礎)
- 問題4(電気回路):45/50
- 問題5(自動制御・情報処理):39/50
- 問題6(電気計測):40/50
🏭 課目Ⅲ(電気設備及び機器)
- 問題7(工場配電):45/50
- 問題8(工場配電):39/50
- 問題9(電気機器):40/50
- 問題10(電気機器):47/50
💡 課目Ⅳ(電力応用)
- 問題11(電動力応用):44/50
- 問題12(電動力応用):26/50
- 問題13(電気加熱):44/50
- 問題15(照明):47/50
所感|エネルギー管理士試験を受けて感じたリアルな本音
ここでは実際にエネ管を受験してみて感じたリアルな本音を語ります。
- 体感難易度
- 4科目受験の疲労感
- 本番特有の緊張感
体感難易度は電験三種といい勝負!
試験直前に実施した過去問演習や電気計算の模試では、4科目すべて余裕を持って合格ラインを超えていたので、「これは一発合格いけるな」と自信はありました。
そして試験本番でも、手応えはバッチリ。受験直後から「全科目、合格点は下回っていないだろうな」と確信していました。
体感的な難易度としては、「電験三種と同じくらいかな」という印象です。
ただ、最近の電験三種は過去問ベースの出題がかなり多くなっているので、それと比べるとエネ管(エネルギー管理士試験)のほうがやや難しく感じるかもしれません。
朝から夕方まで…4科目受験はやっぱりキツい
これは電験三種のときも感じたことですが、朝から夕方まで4科目受験となると、想像以上に体力を消耗します。
特に、エネ管や電験のような「思考力」と「集中力」を要する試験は、試験中にどんどんエネルギーが削られる感覚でした。
課目Ⅲと課目Ⅳは問題数も多く、試験時間が110分もあるので、集中力を維持するのが本当に大変…。
私は栄養ドリンクを持参して、昼休みにチャージ。さらに水分補給も意識して行いました。
余談ですが、当日は真夏の暑さも相まって、エアコンが効き切っていない教室での受験になりました。
しかも机の上にペットボトルを置くのは禁止というルール…。喉はカラカラなのに水分が取れないのはかなり辛かったです。
試験監督からは「体調不良で水分補給が必要な場合は手を挙げてください」と言われたものの、体調崩してからじゃ遅いでしょう!と思いました(怒)
エアコンが効いていなかったのは、エネ管だけに、省エネ運転だったんですかね…?(笑)
本番特有の焦りとの戦い
普段の過去問演習では、時間を測って解いていたものの、本番とはやはり違いました。
緊張感のせいか、解いた後に何度も見直したり、少しでもわからない問題に遭遇すると頭が真っ白になって焦ったり…。
「焦らず落ち着け」と思いながらも、特に課目Ⅳでは時間がギリギリになってしまい、最後まで解ききれなかったのは悔しかったですね。
やはり、電験やエネ管のような試験では、落ち着いて確実に解ける問題から処理していくことが超重要だと改めて感じました。
本番の焦りに呑まれないためにも、普段から「見直し込みで時間を意識した演習」をしておくと安心だと思います!
まとめ|エネルギー管理士試験を振り返って
今回、令和5年度エネルギー管理士試験(電気分野)を受験して感じたのは、事前準備の大切さと本番ならではの難しさです。
過去問や模試でしっかり対策していたおかげで、一発合格することができましたが、それでも本番の緊張感や焦り、体力的な消耗には想像以上に苦労しました。
これからエネ管試験に挑戦する方は、ぜひ「知識」だけでなく「本番での集中力や体力維持」まで意識して準備してほしいなと思います。
そして当日は、落ち着いて、できる問題から一つずつ確実に積み上げていくことが合格への近道です!
この体験談が、これから受験される方の参考になれば嬉しいです。
応援しています!
あわせて読みたい!エネ管(電気) 受験対策のおすすめ記事
エネ管(電気)の受験を考えている方に向けて、他にも役立つ記事をまとめました👇
ぜひこちらもチェックして、合格に向けた準備を万全にしましょう!